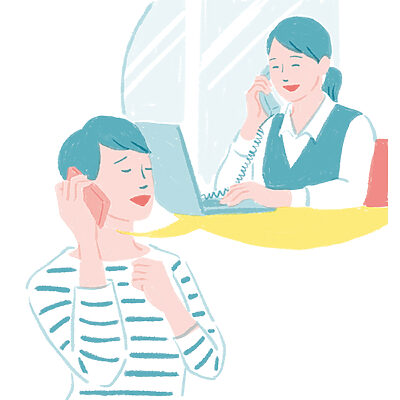考察『光る君へ』47話「命を懸けた彼らの働きを軽んじるなぞ、あってはならぬ!」実資(秋山竜次)に拍手!次回最終回、倫子(黒木華)の言葉のその先には?
文・ぬえ イラスト・南天 編集・アライユキコ
大宰府……

「刀伊の入寇」に巻き込まれた、まひろ(吉高由里子)、周明(松下洸平)、乙丸(矢部太郎)。
矢が周明の胸を貫いた。苦しい息の下で「逃げろ」という周明の体にとりすがり泣き叫ぶまひろだったが、乙丸が力ずくで浜から連れ出して逃げた。
都には私の居場所はない。私はもう終わってしまったのだと泣く彼女に、まだ命はある、書くことはどこででもできると励ましてくれた彼。新たな光が差したかに見えた世界は一瞬で暗転する。
いつの世も、そして虚構でも現実でも、別れは突然であり運命は残酷だ。
一方、都の内裏では摂政・頼通(渡邊圭祐)の前に、慌ただしい様子で蔵人頭が文を届けていた。
蔵人頭「ただいま大宰府より飛駅(ひえき)にて解文(上申書)が届きました」
飛駅とは、律令制において都と地方の間で緊急事態連絡の使いである。これで送られてくること、すなわち非常事態を意味し、傍にいた行成(渡辺大知)の顔色は文面を読む前から変わる。都に届いた隆家(竜星涼)からの報せ。これにより、ようやく、朝廷は九州で起こった惨劇を把握したのである。
頼通「壱岐、対馬の者がどれほど殺められたのか」
行成「この解文では人数はわかりませぬが多くの者が殺されておるやもしれませぬ」
のちの世には「刀伊の入寇」の被害は死者400人以上、攫われた者1000人以上と伝わる。
頼通、この時27歳。若い彼にとっては、この事態はあまりにも荷が重い。太閤・道長(柄本佑)に知らせようと急ぐ行成を、頼通は止める。
頼通「父はもはや政に関わってはおらぬ。心配をかけてはならぬ。黙っておれ」
摂政として自分が国の舵を取らねばという気概と、息子として病の父に負担をかけたくないという気持ちと。この時の頼通には、どちらもあっただろう。
しかし道長には、実資(秋山竜次)がこの緊急事態を報せていた。
道長「大宰府……」
まひろのことを知る百舌彦(本多力)が、実資の背後でそっと反応する。
道長「朝廷が隆家と大宰府を見捨ててはなるまい。すぐに武者を集めて大宰府へ送れ」
実資「敵は大宰府を落とし、海路、都を目指しているやもしれませぬ。山陽道、山陰道、南海道、そして北陸道にも警護の武者たちを差し向けるよう、これより陣定ではかります」
報告と協議を終えて朝廷に向かう実資が出て行ったあとに、道長の心からの一言が漏れる。
「生きておれよ」
まひろの安否はまだわからない。
「同じく」で乗り切ってきた男
道長と実資以外の貴族たちには、都から遠く離れた地で起こったできごとに対する危機感はないと描かれる陣定場面。
左大臣・顕光(宮川一朗太)は、まだ議題を聞いていないうちから右大臣・公季(米村拓彰)に「まかせる」と、大あくび。居眠りを続ける顕光はこの時75歳、公季は63歳。もともと政に志も情熱も燃やしている様子には見えなかった大臣たちのモチベーションが、老いて更に低くなっている。
では、公卿・参議の中で、若手はどうかといえば……。資平(篠田諒/実資の養子)、能信(秋元龍太朗/道長の四男・明子(瀧内公美)の三男)、通任(娍子の同母弟/古舘佑太郎)は「前例がないことゆえ、わかりません」。頼宗(上村海成/道長の次男・明子の長男)と教通(姫小松柾/道長の五男・倫子の次男)は「討つべし」。
行成は「朝廷が武力を振るってはなりません。祈祷をして邪気を払うべき」。現代の感覚では祈祷だけだなんて、なにもしないのも同然では? と思ってしまうが、日常生活から国家の一大事まですべて加持祈祷でなんとかしようとする平安時代の人々の姿を、この作品を通して一年観てきたので、行成の意見もわからなくはない。ただ、なんとももどかしい。
そしてこの人が本人の希望通り太宰府権帥として赴任していたら、今回の事態にどう対処していたのだろうかとも想像を巡らす。
公任(町田啓太)「大宰府のことは大宰権帥(隆家)が取り計らうべき」
俊賢(本田大輔)「しばらく様子を見るのがよろしい」
斉信(金田哲)「朝廷が武力を持つことはならぬが攻め入ってくるものは討たねばならぬ」
道綱(上地雄輔)「同じく」
大納言・藤原道綱、64歳。「同じく」で陣定を乗り切ってきた男。斉信は軍勢での討伐を提案しているのだけれど、それになにも考えず賛同して君は本当にいいのか。道綱はずっと憎めない男として描かれてきたが、いつもの口癖で国家の一大事が左右されるの、とても怖いんですけど。
先週の「刀伊の入寇」の緊迫感、最前線で戦っている武者たち、周明らたおれた民衆を思い出すと、緩んだ陣定の空気に舌打ちしそうになるが、そこに実資が登場した!
実資「敵が都を目指したときの時のために山陽道 山陰道、南海道、北陸道の守りを固めるべし。都の武者だけでは足りぬゆえ急ぎ各地の武者を集めるよう手配すべし」
道綱「めんどうだなーそれ」
さっき、斉信の迎撃案に賛同しとったやんけ! 本当に話をなんも聞いてなかったんだな!と怒りかけたら、実資が目を剥いて「めんどうとはなにごとか」。ほんとだよ。
そして、この結論は先送りにされ、さっさと大臣たちは陣定を切り上げてしまった。
ことは急を要するのだという実資の言葉は無視される。
46話(記事はこちら)で、戦船を国の軍事施設である主船司で調達しようというときに、朝廷の許可を待ってはいられないというやり取りがあった。陣定がこの調子では片道10日かかる連絡手段は仕方ないとして、たとえ当時電話があって事態をすぐに朝廷に伝えられたとしても、戦船の使用許可が出るまでにどれだけの時間を要しただろう。
実資とともに、観ているこちらの怒りのボルテージが上がっていく。
陣定での意見を受けて、幼い後一条帝(橋本偉成)の摂政として決断せねばならない頼通は頭を悩ませていた。
頼通「いくらなんでも都までは攻めてこぬよな」「このまま様子を見よう」
左大臣・右大臣とは違い、攻め上ってくる可能性については考えたものの、結局動かなかった。
道長は頼通を叱責する。
道長「民が! あまた死んでおるのだぞ。お前はそれで平気なのか」
道長は実際に民の屍が累々と積み重なった現場を見ている。鳥野辺で直秀(毎熊克哉)と散楽の皆を、そして悲田院では疫病で息絶えた人々を。世の中を変える力を持つべきだとまひろに励まされて頂に立った彼は今、その力を持っているのに何もせぬ息子を前にして憤る。
しかしその怒りは「父上であろうとそのようなことを言われる筋合いはございませぬ」と家族内での対立として矮小化されてしまった。摂政の座を退いて息子に譲る意志を打ち明けたとき「頼通様にあなたの民を思いやる御心は伝わっておりますの?」と言ったまひろの不安は的中してしまったのだ。
今回は、隆家と武者たちが対馬まで船を出して刀伊を追撃したので、大宰府から東へ敵が進軍することはなかったが、もしこれが海賊ではなく他国の軍であったら日本は滅んでいたかもしれないな……と想像してしまうような貴族たちの描写だった。史実では、ここまで他人事ではなかったはずだと思いたい。実際『小右記』ではこのときの陣定で、山陽道、山陰道、南海道の守りを固めようという意見は大臣から出て、実資はそれに北陸道も加えるべきと述べたと記される。
ドラマでは、居眠りしたり、地方の危機など頭にない様子の中央の政治家を、現代への風刺として描いたのだろう。
ちなみに、刀伊の襲撃によって連れ去られた人々についても『小右記』にある。日本から退散した賊の船は高麗軍とも戦闘となった。このとき高麗によって保護された多くの日本人が丁重な扱いを受けて帰国している。これにより、高麗による攻撃ではなかったという判断になったのである。ただ、これに対しても朝廷が警戒している節はあった。
異国からの侵攻に対して、当時の朝廷は無頓着ではなかったのだ。
まひろを見舞う隆家
乙丸の力で大宰府に無事帰ることができたものの、まひろは憔悴しきっていた。
無理もない。目の前でまた大切な存在を奪われたのだ。母・ちやは(国仲涼子)といい直秀といい、たね(竹澤咲子)といい。生きるということは、愛しい人々を見送るということでもある。
そんな彼女を、隆家が見舞う。
隆家「俺も色々あったが……哀しくとも苦しくとも人生は続いてゆくゆえ。仕方ないな」
大切な家族を喪い続けた隆家が辿り着いた「仕方ないな」。投げやりな意味ではなく、現実と向き合わねばならなかった人間ならではの温かい言葉だ。
まひろが最後に見た周明はまだ息があったので、もしかしたら助かったのかもという淡い期待を抱いたが、彼の骸は弔われることなく死んだ賊たちとともに海風にさらされている──。いずれ土に還ってゆくことだろう。さようなら、周明。お疲れ様でした。
隆家からの報告によって、「刀伊の入寇」の終結を道長に報告する実資が、朝廷も武力を持つべきではないかという話をする。
実資「平将門の乱以降、朝廷は武力を持たなくなりました。それから80年が経ち、まさかこうして異国の賊に襲われることになろうとは……もはや前例にこだわっていては、政はできぬと存じました」
平将門の乱。大河ドラマ『風と雲と虹と』(1976年)でも描かれた、桓武天皇の血を引く軍事貴族・平将門が935年に起こした関東での内乱。これについて書き始めたら10ページあっても足りない。とにかく武者という存在を朝廷が強く意識せざるを得なかった歴史的大事件である。よくぞここから80年以上、大きな戦をしない世を保てましたねと先人たちの努力と知恵に敬意を払いたくなる。
実資の言葉に「武力に頼る世になってはならん!」と反対する道長。この理想は時代の波に流されて、儚くなってしまうのだろうか。
しかし、その話が終わると、
「大宰府の隆家に文を出すなら消息を聞いてもらいたい者がおるのだが」
まひろのことが心配で仕方がないんだね……離れた地にいる人の安否がわからないと夜も眠れないほどの不安に襲われる気持ちはわかる。
でも実資に頼もうとするくらいなら、もてなしを命じた時と同じように隆家に直接「太皇太后様の女房・前越後守為時の娘は無事か。太皇太后様がいたくご心配あそばされておる」と文を書いてもいいと思うのよ、道長。
秋山竜次に拍手を
隆家たちの刀伊撃退の功績についての褒章を協議する陣定が開かれた。
朝廷に報告が届いていない期間に行われた戦闘、朝廷の命令でない戦。それに褒章を出すことはできないと主張する、行成と公任。
実際、これまでこの作品の中でも(33話/(記事はこちら)寛弘3年(1006年)、朝廷の許しなく合戦を繰り返す平維平(たいらのこれひら)を伊勢守に任じるなどもってのほかという議論があった。朝廷が武力を持つ者を制御する点を重視する、そういう意味では公任の「前例を見ても」は筋が通っている。
通ってはいる……が、しかし。外敵から民を守った者の戦闘を「関わりなき戦」と言われるのは、納得が行かない……とフラストレーションが溜まりにたまった瞬間、実資が叫んだ。
「なにを申すか!」「敵を撃退した者に褒章を与えねば、この先ことが起きたとき奮戦する者はいなくなるであろう」「都であぐらをかいていた我らが、命を懸けた彼らの働きを軽んじるなぞ、あってはならぬ!」
実資ーーーー!!!! 全国で実資コールが巻き起こったのではないだろうか。
藤原実資という名前は、歴史好き、平安時代好き以外にはおそらくそれほどに知られていないと思う。しかしこの一年で、俳優・秋山竜次がその名前と存在を視聴者に知らしめたのだ。大河ドラマファンには忘れられない人物となっただろう。好演に拍手喝采である。
『和漢朗詠集』だ!
その夜、道長が実資の陣定の結果報告を聞いているところに、公任が訪ねてくる。
この場面、わかるようでわからない。
公任「俺達にはそんな姿見せぬのに、実資殿には見せるのだな」
(突然どうした、わからない)
公任「隆家はお前の敵ではなかったのか! ゆえに俺は隆家をかばわなかった、お前のために!」
(国家の危機と政争を天秤にかけたのだな、わかる)
道長「国家の一大事にあっては隆家の前に起きたことの重大性を考えるべきである」
(それな)(わかる)
まあまあ、と仲裁に入った斉信「なにがあっても俺は道長の味方だから」
(いやだから、突然どうした。わからん)
わからん……とポカーンとしていたが、翌日『和漢朗詠集』を開いて眺めている公任を行成が訪ねてきた場面で、はたと気づいた。
公任が編纂し行成が清書した『和漢朗詠集』! 当時の貴族社会において重要な文化であった朗詠。それにふさわしい漢詩、漢文、和歌を集めたものだ。その後の日本文学……『平家物語』などの軍記物にもこの書から詩歌が数多く引用され、貴族・武家ともに必須の教養書となっていった。日本の文化全体に及ぼした影響ははかりしれない。朗詠のお題が並んでいて、ドラマの中で公任が見ているのは「祝」の章。ここに、今の私たち誰もが知っている和歌が美しい手蹟で書かれている。
わかきみはちよにやちよにさされいしのいはほとなりてこけのむすまて
(我が君は千代に八千代にさざれ石の巌となりて苔のむすまで)
『古今和歌集』から、読み人しらずの歌。そう。国歌「君が代」の元歌である。
このように、のちのちまで多くの人が触れることになる詩歌が集められた書だ。今でも現代語訳つきの本が出版されているので、ぜひ「公任様のみが成しえた大仕事」を読んでいただきたい。
公任の怒りの場面はよくわからなかったが、四納言の皆が道長を大切にしているのはわかった。
双寿丸の言葉
「刀伊の入寇」の恩賞が自分が求めた通りにならなかったとはいえ、隆家は大宰府の皆に語り掛ける。
隆家「武者たちが国守となり各国の要となって働けるよう、この先も朝廷に働きかけ続けるゆえ」
……あー。実資が陣定で激昂した場面でも思ったのだが、朝廷の力が及ばないところでの戦闘が頻発するようになったらどうなるのか。国守となった武者たちは、この先もずっと朝廷の命令に従うのか。
私たちは、この後何が起きるのか、どんな時代になってしまうのか知っている。が、その時代に真摯に生きていた人々を裁くことは私にはできない。
これからの世を生きてゆく若者・双寿丸(伊藤健太郎)が「殺さなければ殺される。敵を殺すことで民を守るのが武者なのだ」とケロッとして明るく言うのが象徴的である。
乙丸一世一代の我儘
まひろの身を案じ続ける道長が、ようやく(この手があったか)と気づいたようで、娘の賢子(南沙良)に母からの文はあったかと消息を訊ねる。
まひろは生きていた……! 安堵のため息。よかったっすね。そして賢子に、
道長「太皇太后様にはお目をかけていただいておるか」
賢子は道長の慈しむような視線の意味がわかっていない。
この世に、ただ健やかでいてくれればそれでいいと思える人がいる。道長にとっても賢子にとっても、そうした存在であるのが一番いいのだ。
隆家が太宰権帥の任を解かれて都に戻る。隆家がまひろに「共に都に戻らぬか」と問うが、意気消沈しているまひろは答えあぐねる。そこに乙丸が、
「御方様! 私はきぬに会いとうございます!帰りましょう!帰りたい!帰りたーい! きぬに会いたーい!」
乙丸は今までどんなことがあっても、まひろにもその家族にも意見を言うことはなかった。その彼が、必死に我儘を装ってまひろを都に戻そうとしている。一世一代の我儘だ。
目頭が熱くなり、都の大路を隆家一行と帰ってくる乙丸の笑顔に泣いてしまった。乙丸は、彼の一生の願い「今度こそ御方様をお守りする」を果たしたのだ。
よかったね、よかったね……。
そして、きぬ(蔵下穂波)にお土産の紅を渡す場面にまた泣いた。ここは厨の外から、ふたりの様子をそっと窺っているような画面演出もいい。紅を見て大喜びするきぬ。本当によかったね……乙丸ときぬの夫婦に幸多かれ。
帰還した夜、『源氏の物語』を感想を母に伝える賢子。賢子の「母上は私の母上としてはなっていなかったけれど」という批評に思わず笑ってしまう。しかし、その才能は認める。
親を客観的に冷静に見られるのが大人の証である。立派だ、賢子。
そして彼女が物語から得たものは、政の頂に立っても、好きな人を手に入れても、よい時は束の間。幸せとは幻。
賢子「どうせそうなら、好き勝手に生きてやろうかしらと思って」
まひろ「よいではないの! 好きにおやりなさい」
物語を通して、娘の背中を力強く押すことができた。これぞ母親としての本懐であろう。
まひろも立派だよ。
さすがだぜ倫子様!
旅から帰り、土御門殿に住む太皇太后・彰子(見上愛)に挨拶したまひろは、その帰りに道長とばったり会う。出家した彼を初めて見る、生きていてくれと願った彼女を再び目にする──。ふたりのまなざしからは、愛欲も恋情も越えて、そこにいてくれることこそが人生の喜びだというところにまで達したことを感じた。
そこに「藤式部。北の方様(倫子/黒木華)がおよびです」と声がかかった。倫子の居室に向かうまひろの視界には、はじめて土御門殿に来たあの日が再現されていただろうか。そして、倫子も「あなたが初めてこの屋敷に来た日のことを思い出したわ」。懐かしい昔語りの流れでごく自然に、
倫子「それで。あなたと殿はいつからなの? 私が気づいていないとでも思っていた?」
固まるまひろ、固まるテレビの前の我々! 全国を一瞬で凍らせる……さすがだぜ倫子様!
次回予告。本当に好きに生きる賢子。俺たちの祖・菅原孝標娘登場! 双寿丸、完全に武者。明子様お元気だった! 道綱は道綱。ききょう様とまひろ様が再会。もう泣きそう。
みんなみんな、お別れなんですね……最終回、12月15日放送!
*******************
NHK大河ドラマ『光る君へ』
公式ホームページ
脚本:大石静
制作統括:内田ゆき、松園武大
演出:中島由貴、佐々木善春、中泉慧、黛りんたろう
出演:吉高由里子、柄本佑、黒木華、見上愛、南沙良、岸谷五朗 他
プロデューサー:大越大士
音楽:冬野ユミ
語り:伊東敏恵アナウンサー
*このレビューは、ドラマの設定(掲載時点の最新話まで)をもとに記述しています。
*******************