不正出血したら、すぐ受診。子宮体がんは治りやすいがんです。
撮影・森山祐子 イラストレーション・小迎裕美子、川野郁代 文・越川典子、青山貴子

子宮がんには、頸部(けいぶ)にできる子宮頸がんと体部(たいぶ)にできる子宮体がんがある。
子宮頸がんは、20〜30代に多くみられ、初期のうちは自覚症状がほとんどない。しかし、子宮の入り口付近に発生するため、婦人科の診察や検査などでも発見しやすく、20歳以上なら自治体で1〜2年に1回(自治体によって異なる)、検診を受けることができる。
それに対して、50代をピークに40代以上の女性がなりやすい子宮体がんは、自治体の検診対象にはなっていない。
そのため、検診を受けたことのない女性も多いが、早い段階から不正性器出血があるケースが95%も。つまり出血したら、まず原因をスクリーニングする必要があるのが、子宮がんなのだ。出血を見逃さなければ、早期発見しやすいがんでもある。
患者数は以前は子宮頸がんが圧倒的に多かったが、2000年代になって子宮体がんが急増。そこで、婦人科がんの医療に30年以上携わる加藤友康さんに子宮体がんについて聞いた。
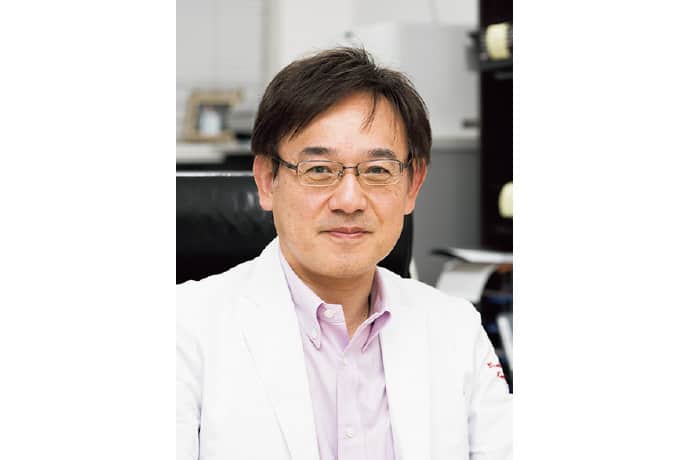
子宮体がんの代表的な自覚症状は、不正性器出血。ところが40代になると生理周期が乱れたり、閉経間際は出血が止まりにくくなることもあるので、子宮体がんの不正性器出血なのかがわかりにくい。そのため、「出血が止まるまで待とう」と検査を先送りにしてしまう女性も少なくない。
「出血が2週間以上続いたり、閉経後に出血があった場合、出血が止まるのを待たずに、まずは子宮体がんの検査を受けて、内膜の状態を把握することが大切です」と加藤さん。

出血したら受診したい。 先送りにしないこと。

子宮体がんの検査は、まずはブラシやストローのような検査器具を使い、内膜の細胞を採取する。その結果、疑わしい場合は、組織の一部を切り取る組織診で確定診断を行うが、組織診は多少の痛みを伴う。また、更年期以降になって腟が萎縮してしまうと、検査器具が入らないこともある。
「痛みには個人差がありますが、エストロゲンの錠剤を何日前からか飲んでもらったり、麻酔を使ったりする場合もあります。腟萎縮でどうしても検査ができないときは、超音波やMRIで子宮内膜の厚みを診断します」
子宮頸がんの検査は自治体の定期検診の対象になっていることもあり、子宮がんの中でも患者数が多いのは、子宮頸がんというイメージが強い。
「しかし、2000年代には逆転し、2016年には、子宮体がんの新しく登録された患者数は1万1085人で、子宮頸がんの7784人を大幅に上回っています」
【子宮体がんの診察の流れ】作成:加藤友康
1. 問診
所定の質問票に妊娠・出産の有無などを記入。この質問票をもとに医師から質問がある。
2. 外診
患者の身体を、医師が目と手でもって診察する。
3. 内診
腟内に腟鏡を入れて観察する腟鏡診、医師が子宮の大きさや向きを調べる触診がある。
4. 細胞診
ブラシやストローのような専用の器具を子宮内腔に入れ、粘膜をこすったり、吸引したりして細胞を取り、顕微鏡で調べる。
5. 組織診(確定診断)
細胞診で疑わしい結果が出た場合、子宮内膜組織を採取して顕微鏡で調べる。これが確定診断となる。細胞診と同時に行うこともある。
広告


































