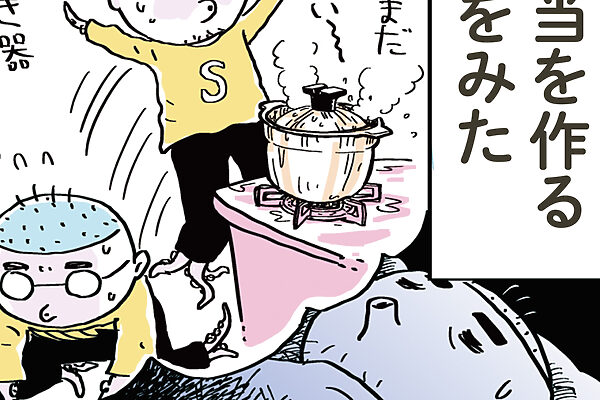【前編】いつか土になる「くさる家」で暮らす心地よさ。
撮影・尾嶝 太

黒い板張りの外壁の前に薪を積み、ゆるやかな傾斜を描く屋根は洗練された印象の鉄板。上の写真のシックな家は、実はもともと築200年を超える古民家。霞が関や新宿などの超高層ビルを手がける大手建築設計会社に勤めていた今井博さんが、仕事をしながら週末や夏休みなどを利用して、年間60日ほど通い6年をかけて改修した姿だ。購入当時のスナップ(中段の写真2枚)を見るとあらためて、その変貌ぶりに驚かされる。
「ぼろぼろに見えますが、フレームがしっかりしていたのでおもしろいと思いました。ゆがみを職人に直してもらい、構造はほぼそのまま使っています。外壁や内装は、地元の木を使う方針で私がつくり直しました。居間の床にしたアカマツは、木立から選んで伐倒してもらうところからやっています。家具工房として使うつもりが、木の家が快適で移住することに」(博さん)

今井邸を紹介してくれたのは、建築家など住宅に関わるプロの女性4人のユニット「つなが~るズ」。東日本大震災で瓦礫と化した家屋を見て、衝撃と脱力感とともに自分たちの仕事を振り返り、土に還る素材など環境に負荷をかけない「くさる家」こそ、追求すべきではないかと感じたという。
「そもそも日本の民家は完璧な『くさる家』でした。石に柱や束つかを立てる石場建てで、その土地の木、土、草という素材だけでできていました」(林美樹さん)
「殿様でもない限り、そこにあったものでしか、家をつくることなんてできなかったんですよね」(神田雅子さん)
土に還る素材でつくる家には、ストローベイルハウスもある。藁のブロックを積み上げて、漆喰などで仕上げるもので、次世代にツケを回さない点で注目されている。この工法でつくられた建物が今の日本にも少しはある。
「なかなか普及しないのは、藁という材料が流通していないから。それに法的に防火のための審査が厳しい地区には建てられないのです」(林さん)
「壁が厚いので、土地に余裕がある敷地でないとむずかしいですね。高温多湿の日本の風土に本当に合っているか、ちょっと疑問ですし」(平山友子さん)

一方、地元で採れる素材は運搬にエネルギーがかからず、間違いなくその土地の気候に適応している。林さんも自ら設計した家を建てる時はまず、地元の木を使うことを施主に提案している。
「できるだけ地元の材料を使って、その土地の大工さんに建ててもらうようにしています。東京なら多摩産材があります。そして、昔ながらの小こまい舞土壁をおすすめしています」(林さん)
自然の木も土壁も、湿気のある時は吸い、乾燥している時は出す、調湿能力が高く、よい香りがする。実際に、空気の質が格別だという。
「私は、木の家を設計している割には、マンション住まいで、床は塗装された合板フローリング、壁はビニールクロス。湿度の高い日はもうベタベタで、においも残る。音の響きも硬いし、足にも硬い。体に影響しますよ」(林さん)
「ここは音の響きがよくて楽器が上達した気がするくらい。たまに東京に行って、戻ってくるとほっとします」と、改装時から一緒に足を運んでいた妻の今井富美恵さんも同意する。
『クロワッサン』937号より
●つながる〜ズ 建築設計事務所を主宰する、今の時代にあるべき木の建築を追い求める神田雅子さん、伝統を今に生かす木組みと職人技術による住宅を手がける林美樹さん、幕末の長屋を拠点に歴史ある町の再生に取り組む住宅ライターの平山友子さん、シックハウスの専門家である濱田ゆかりさんの4人によるユニット。東日本大震災後、SNSを通じて親交を深め、環境に配慮した暮らしにまつわる提案などの活動を推進中。著書に、『くさる家に住む。』(六耀社)。
広告