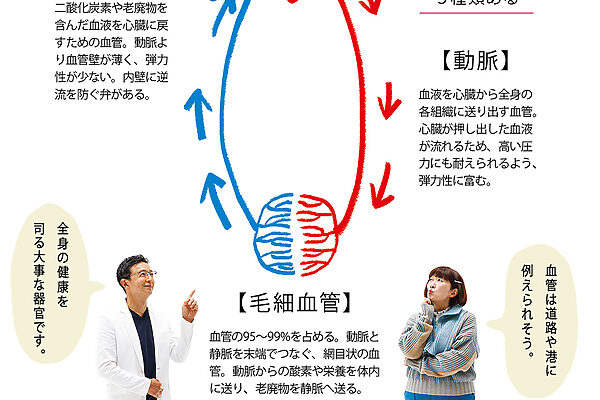「大きな鳥にさらわれないよう」川上弘美さん|本を読んで、会いたくなって。
人間という種の終末世界を描きたかった。

ひとつひとつ、小さな物語を楽しんでいたら、突然世界が開けてきて、あとはもうまっしぐら、大きな物語に飲みこまれていく。ここにあるのは、未来の神話だ。
「最初の章の『形見』は独立した短編で、それを書き上げたときに、この〝世界〟のことをもっと書きたいなと思いました。地震の経験は大きいです。災害があったことで反対に、戦争をしながらも人類が地球上で繁栄していることは生物の種としてはとても運のいいことだと感じましたし。でも永遠に続く種はたぶん無い。種が終わる、もしくは終わらないかもしれない、その時に種全体は何を考えどうなっていくのかということを書いてみたかった」
紡ぎだされるのは途方もなく長い時間の物語ーーイルカや兎を由来に工場で作られる人間。名前のない「私」が世代を継いで
果たす「見守り」。たくさんの優しい母たちと特別な大きな母。互いを食い合い(愛をもって)、光合成をする人たち。はっきり語られることのない災厄を経て、人間は数を減らし、隔絶された小さな集団で暮らす。章ごとに視点も文体も切り替わり、いつのまにか読者は大きな物語の中にいることになる。
「書いているときは、すごく楽しかったです。小説家としては、今まで自分が使ったことのない語り方で書く、という欲望がありますが、それをまず試せたということ。原稿用紙10枚でデビューして、100枚書けるようになるまでがすごく大変で。それが一歩ずつ……書く筋肉をつけてきて、そうして今、その筋肉を全部使って書くという楽しさがありました」
物語の中でクローンやAIなど、今まさに現実世界で話題になっている事象も大きな役割を果たす。
「(本の発売時期と)タイミングが合ったのにはびっくりしました。でも、そもそも私、大学は生物科、SF研究会だったりして、久しぶりに好きな世界に戻ってきたなという感じも(笑)」
壮大な世界を描きつつも、視線は温かく、すぐそばにあるような。川上作品が生まれる背景を少しだけ教えてもらった。
「原稿用紙を四つ切りにして作ったメモ帳をいろんなところに置いておいて、朝起きたときだったり、夜寝るときだったり、何か思いついたらすぐ書いて。どんな小説を書くときも同じです。実際にそのメモが役に立つかどうかはさておき、暮らしの中で思いついたカケラがカタチになっていく。何かが始まる感じがありますね」

広告