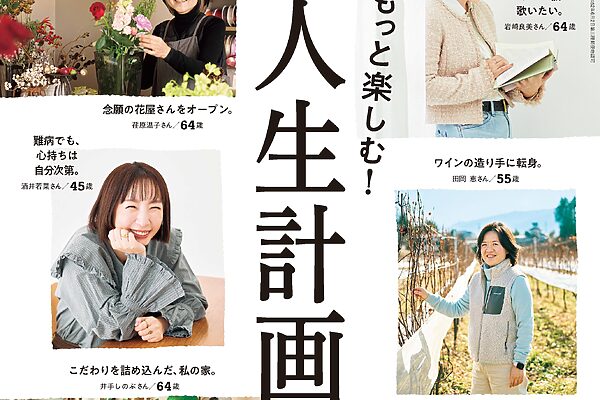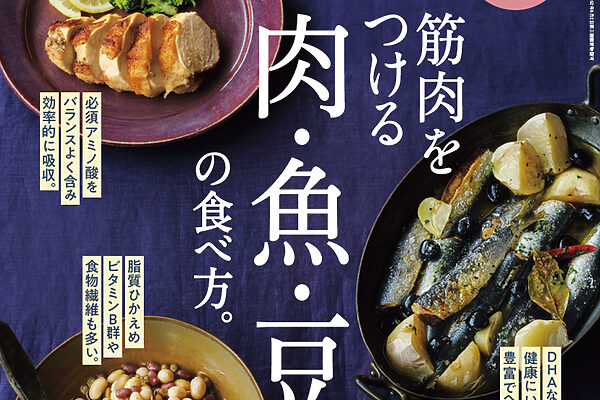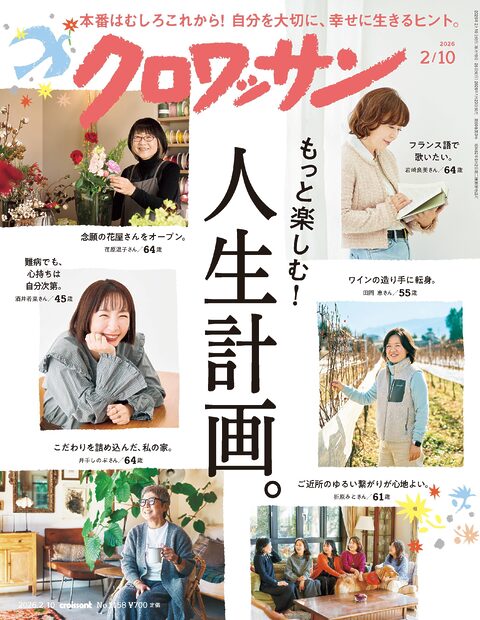嵯峨の香りを伝える華麗な障壁画ーー「旧嵯峨御所 大覚寺—百花繚乱 御所ゆかりの絵画—」展
皇族や貴族が住職を務めた門跡寺院・大覚寺。その寺宝を紹介しているのが、東京国立博物館で開催中の本展「旧嵯峨御所 大覚寺」だ。2月6日には天皇、皇后両陛下と愛子さまが訪れ、さらに話題を呼んだ。
文・青野尚子
平安時代、風光明媚な嵯峨の地に嵯峨天皇が造営した離宮「嵯峨院」。貞観18年(876年)、嵯峨院は寺となり、「大覚寺」が開創される。特別展「大覚寺」はこの大覚寺に伝わる寺宝を紹介するもの。
中でも寺内の「宸殿(しんでん)」と「正寝殿(しょうしんでん)」を飾る障壁画の展示は圧巻だ。全約240面の襖絵や障子絵は一括して重要文化財に指定されている。この多くを手がけたのが安土桃山時代〜江戸時代に狩野永徳の愛弟子として活躍した狩野山楽(かのうさんらく)と、江戸時代中期の絵師、渡辺始興(わたなべしこう)だ。
現在、これらの障壁画は14年に及ぶ大修理の途中だが、修理を終えたものを中心に前後期あわせて123面が展示される。
障壁画のうち「牡丹図」は宸殿の「牡丹の間」を飾る襖絵だ。金地に岩や雉の親子とともに赤や白の牡丹がリズミカルに配置され、狩野山楽の優れたデザイン感覚を思わせる。宸殿の「紅梅の間」の「紅白梅図」は連続する襖に太い幹が伸び、枝には満開の紅白梅が咲き誇る。師・狩野永徳ゆずりのダイナミックさと山楽の洗練された画風が融合した傑作だ。渡辺始興が正寝殿「狭屋(さや)」の腰障子に描いた兎の板絵も愛らしい。
会場には通常非公開の正寝殿のうち「御冠(おかんむり)の間」の再現も登場する。平安後期の仏師、明円作の「五大明王像」(本尊)が5体そろって東京で展示されるのも初めての機会だ。
歴代天皇の書なども並んで、大覚寺が大切に守ってきた美と信仰の心が味わえる。

大覚寺は皇族や貴族が住職を務めた「門跡寺院」であり、皇室ゆかりの品々を多数所蔵している。応仁の乱などの動乱を乗り越えて受け継がれた宮廷文化の華やかさが感じられる。
『旧嵯峨御所 大覚寺―百花繚乱 御所ゆかりの絵画―』
開催中~3月16日(日)
開催中~3月16日(日)
東京国立博物館平成館(東京都台東区上野公園13・9)
TEL.050・5541・8600(ハローダイヤル)
9時30分〜17時 月曜、2月25日休(2月10日、24日は開館)
入館料一般2,100円ほか
TEL.050・5541・8600(ハローダイヤル)
9時30分〜17時 月曜、2月25日休(2月10日、24日は開館)
入館料一般2,100円ほか
『クロワッサン』1134号より
広告