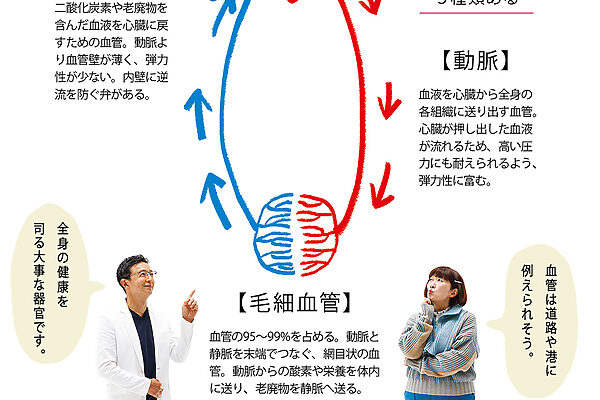『カザアナ』著者、森 絵都さんインタビュー。 「生きづらい世の中に風穴を開けたかった」
撮影・黒川ひろみ(本) 土佐麻理子(著者)


「未来を描く作品に挑戦したかったんです」と森絵都さん。
舞台は東京五輪から約20年後、国民を見張る「ドローンカイト」が飛び回る監視社会。日本至上主義が謳われ、国の方針に合わないものは容赦なく排除される。
「今の日本にも窮屈さを感じることはあって、時代が進んでこれがもっとエスカレートしたらと恐ろしくなった。そこで、息苦しい世の中に“風穴”を開けてくれるような物語を作りたくなりました」
「風穴」は平安の世に生きていた、自然界との不思議な交感能力を持つ一族。平安時代の末に起きた凄惨な事件で根絶やしになったと思われていたが、実は3人の末裔が生き残っていた。それぞれ、石・虫・空と心を通わせている彼らは「カザアナ」という園芸会社を営んでいる。そして、ある家族との出会いをきっかけに、閉塞的で生きづらい世の中を変えていく。
「超ハイテク社会に対して、自然界のアナログな力で立ち向かったら面白いだろうなと。この作品を書いている間、どうにも集中力が切れてしまった時期があって。日帰りで京都の庭園を見に行ったら、帰りには嘘みたいに元気になって、一気にエピローグまで書き上げることができたんです(笑)。自然には何か不思議な力がありますよね」
どんなに苦しい世界であってもユーモアのセンスがあればいい。
ジャーナリストのシングルマザー・由阿(ゆあ)、中学生の姉・里宇(りう)、そして小学生の弟・早久(さく)。監視社会に反発している入谷家と親しくなったカザアナは、彼らを手助けするために自らの能力を使うように。
しかし、「大義名分のために能力を使い、血で血を洗うような闘いは描きたくなかった」という。
確かに、早久を封じ込めようとする小学校の校長に対抗するため、虫を操り、超巨大クワガタを召喚するなど、思わず笑ってしまうような方法で奮闘するのだ。
「昔から、嫌なことがあったら真っ向から闘うのではなくどうやってすり抜けられるかを考える性格で。入谷(いりたに)家のためにカザアナがやった一見くだらないようなことが、結果的に世界を変えていたというようにしたかった。描きたかったのは監視社会の恐怖ではなく、それをどうやって楽しみながらすり抜けるかということ。どんなに苦しい世界でも、そこにユーモアのセンスがあればうまくやっていけると思うんです。ユーモアのない世界こそ一番怖いですよね」
物語は家族、学校とスケールを広げていき、ついに子どもたちはアメリカ大統領と会うことに……。
「入谷家には、日本至上主義の社会で抑圧された家族の代表として登場してもらうつもりでした。だけど書けば書くほど、カザアナの力なんていらないのでは、というほどパワフルに突き進んでいく。特に、由阿は他人の家にこっそり侵入したりと、大胆な行動ばかりするので書くのが楽しかったです」
作家生活30年目を迎えた森さんの想像力がこれでもかと詰まったファンタジーが今ここに。
『クロワッサン』1006号より
広告