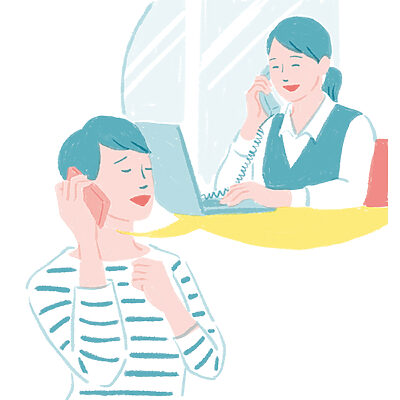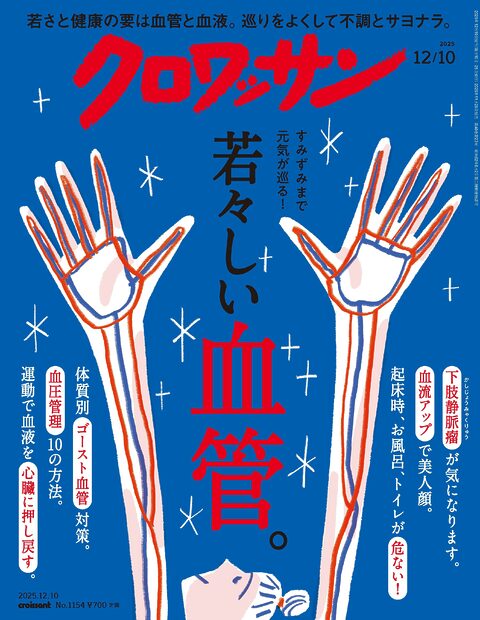腸の健康を支える食物繊維の働きと摂り方を管理栄養士に聞きました。
撮影・黒川ひろみ 文・韮澤恵理
発酵食と食物繊維で腸の環境はぐんぐんよくなる。
腸内を整える菌たちと食物繊維の共同作業。
腸の環境をよくするには腸内細菌のバランスが大切です。善玉菌が増え、悪玉菌が減る弱酸性の好ましい状態を作るためには、まず善玉菌にたっぷりエサを食べてもらうのがポイント。元気になった善玉菌がせっせと乳酸、酢酸や酪酸などの短鎖脂肪酸を生み出せば、弱酸性のよい腸内環境になり、腸粘膜の細胞を強くすることもできます。
善玉菌のエサは食物繊維。食物繊維の多い食事をすること、発酵食から菌を摂ること、この2つで、しっかりエネルギー補給をし、酸を作る好循環に。
食物繊維はヒトには消化できないけれど、腸内細菌にはエサになるのがポイントで、「プレバイオティクス」と呼ばれています。
発酵食が体にいい理由の一つは多くの人が期待するように、生きた菌を腸に届けることですが、それは乳酸菌やビフィズス菌などの一部の菌だけ。しかもヨーグルトなどで生きた菌を届けても一時的に腸内細菌と一緒には働きますが、長くすみつくことはありません。いわば腸内をきれいにする仕事の短期アルバイト。
アルバイトを人手として雇えば一時的に状況は改善しますが、腸内にいる本職の腸内細菌の居心地をよくして、もっと活躍してもらうことを考えるのが得策です。
そう考えると腸のためには発酵食に含まれる菌と、食物繊維を両方バランスよく食べるのが理想。特に食物繊維は多くの人が必要量を摂れていないので、意識して食べたい食材です。
食物繊維はゆっくりと消化管を進み、腸の動きを応援したり、腸の粘膜を健康にする作用もあるので、腸内の不要な物が排泄され、一定数は存在する悪玉菌の出す有害成分などをすみやかに外に出し、善玉菌が悪影響を受けないようにしてくれる働きも。
いろいろな発酵食に、食物繊維の多い野菜や海藻、きのこなどを組み合わせたバランスのいい食事を心がけましょう。一品にしなくても、献立全体に含まれていれば大丈夫です。
発酵食と食物繊維が手を組むと…

●免疫力を上げる
腸にある免疫器官は善玉菌とそれを支える食物繊維で腸内環境が整うと機能アップ。微生物は異物なので、免疫反応の訓練にも。
●便を押し出す
腸内での食物や便の移動を助けるのが微生物と食物繊維。腸内環境が整うと、腸壁を健康にし、毒素の再吸収を防ぐ。
●腸内細菌を増やす
発酵食に含まれる繊維を腸にすむ菌が食べるとエネルギー源に。元気になった善玉菌が繁殖すると腸内がよい環境に。
●消化吸収を正常にする
発酵食で分解され、消化がよくなった食物は、腸に負担をかけずに吸収される。食物繊維は腸内の食物をリズミカルに運ぶ手助けも。
【脳腸相関】
腸の調子がいいと脳に知らせるネットワークがあるので、腸の調子がよくなると自律神経が整う。
『Dr.クロワッサン 強い腸をつくる、発酵食の摂り方大百科。』(2021年2月18日発行)より。
広告