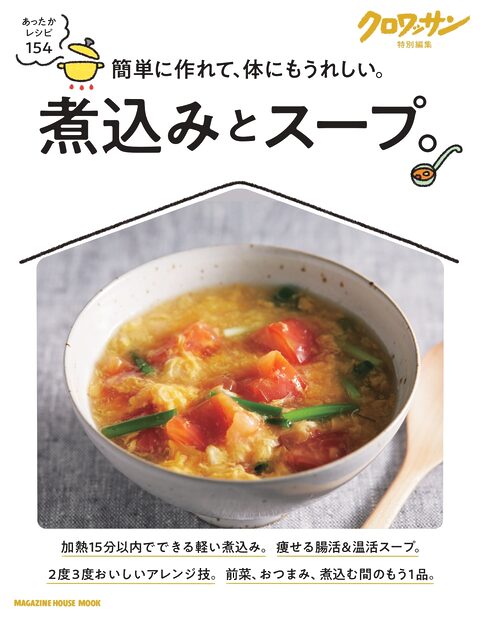食べることは、生きること。人生の最期にアジフライを食べたい──長谷川記三子さん 在宅と病院の間のケア(2)
撮影・井手勇貴 構成&文・殿井悠子

「あなたは人生の最期に、何を食べたいですか?」
埼玉県狭山市にあるハピタルハウスは、病院と介護施設の中間、看護師が主体となって人生の最期の時間を支える“看護の家”だ。医療的ケアに対応しながら、暮らしの延長として過ごせるこの場所では、入居時に必ず冒頭の質問をする。たとえ点滴で栄養を補うことができても「もう食べられません」と言われた瞬間、それが人生の“終わり”の宣告のように感じられることがある。本人に「食べたい」という感覚が残っていると、食べるという行為が止まった瞬間、生きている実感が薄れてしまうように思えるのだ。
入居者が人生の最期に食べたいものは、豪華な料理ではない。あんぱん、アイス、カップラーメン。そこには、その人が生きてきた時間や記憶、日々の暮らしの風景がそのまま詰まっている。
ある末期がんの男性は、鼻から管で栄養を流す経管栄養になり「もう口からは食べられない」と言われていた。それでも願いは、「アジフライが食べたい」。無理をすれば、誤嚥性肺炎になる危険がある。ハピタルハウス代表で緩和ケア特定認定看護師の長谷川記三子さんは、家族にこう伝えた。
「尊厳を守ることは、必ずリスクと背中合わせです。それでも、私たちと一緒に引き受けますか」

家族の了承のもと、医師、看護師、ケアスタッフが薬の調整、嚥下訓練、食事の姿勢などのリハビリを重ねた。約1カ月後、その男性は、家族やスタッフに見守られながら、一口のアジフライを口に運んだ。ゆっくり噛みしめ、飲み込む。その瞬間、表情がふっと緩んだという。
食べることは、生きることだ。単に栄養を摂る行為ではない。好きな味を感じることは、「自分はまだ自分でいられる」という感覚を呼び戻す行為でもある。食べたいという気持ちは、心だけでなく体にも力を与える。その小さな意欲が、呼吸を整え、表情を変え、生きる時間を支えることがある。ハピタルハウスではほかにも、体が動かなかった人が大好きだった日本酒を飲むためにリハビリを続けて、自分でお猪口を持ち上げ最後の一滴まで吸い取るように飲み切ったという話もある。「医学的には解明できないような、人間の奥底にある生きる力を、ここではたくさん見られるんです」と長谷川さん。
安全の名のもとに、すべてを制限するのではなく、危険を理解した上で、その人が選ぶ生き方を支えること。それは、その人らしく生き切るための、大切な選択なのだ。
『クロワッサン』1158号より
広告