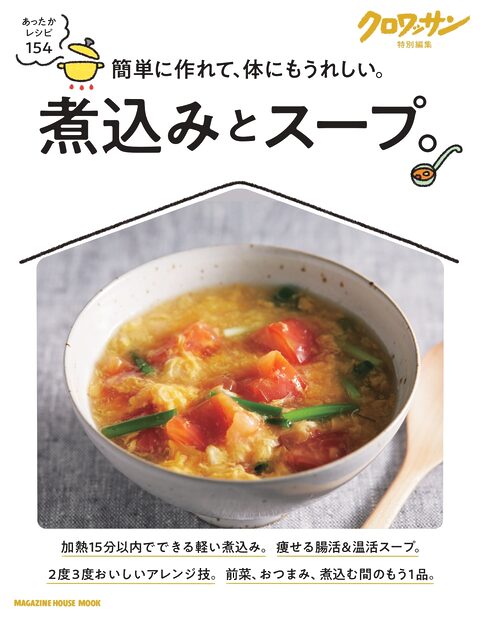考察『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』40話 蔦重(横浜流星)「お前の絵が好きな奴はお前が描けなくなることを望まねえ」歌麿(染谷将太)「欲なんて、とうに消えたと思ってたんだけどなあ…」
文・ぬえ イラスト・南天 編集・アライユキコ
蔦重と鶴屋

曲亭馬琴、葛飾北斎が登場。そして喜多川歌麿の美人画確立への模索。
日本の美術と文学の歴史に、新たな波がやってくる気配がする。
40話はそのエネルギーに満ちていた。
蔦重(横浜流星)が彼らを発掘、プロデュースする姿に胸躍った。
寛政3年(1791年)、耕書堂から山東京伝(古川雄大)作『箱入娘面屋人魚』が刊行される。
この本の序文には、「板元 蔦唐丸」(耕書堂主人・蔦屋重三郎)が挿絵で登場し、「まじめなる口上」を述べる。
「作者の山東京伝は、最近起こした不祥事を恥入り、二度と戯作は書かないと私どもへ伝えたのでございます。が、私ども本屋の商売上、それは困るということで頼み込みまして、長年のつきあいもあるからと、なんとか書いてもらえましたのが本作でございます」
だいたいこんな感じだ。奉行所から二度のお咎めを受けた後の黄表紙で、しぶしぶ執筆したものですよという京伝のアピールだろう。
『箱入娘面屋人魚』は、漁師の船に「お嫁さんにして!」と飛び込んできた人魚が吉原で花魁になったり、漁師と一緒に若返りビジネスを始めたりという珍妙な物語。
人間ではなく人魚だからセーフになるようなエロスが散りばめられた笑い話だ。
だが、世間の反応は冴えなかった。
幕府からの刑罰を逆手に取った「身上半減の店」耕書堂ブームはあっという間に去った。あんなにも賑わっていた店内がガランとして……なんという寂しさよ。
資産半分没収に、多額の借金もある。懐が苦しい蔦重は、再印本をやってみようかと思いつく。
過去の名作黄表紙の板木を他社からも安く仕入れて復刻本を出すというものだ。
鶴屋喜右衛門(風間俊介)が昔の板木を譲ってくれることとなった。ただし、京伝が新作を書くよう働きかけるのに協力するという条件付きで。
蔦重「合点承知です!」
蔦重と鶴屋。地本問屋が力を合わせる姿は、毎回なにが起こるんだろうと楽しくなる。
曲亭馬琴と葛飾北斎
幕府からの仕置きを恐れる京伝は、蔦屋と鶴屋の執筆依頼に応じず、「俺の代わりに、この人書けます」と、戯作者・滝沢瑣吉(さきち/津田健次郎)を紹介する。
瑣吉「困っておるなら書いてやってもよいぞ、本屋ども」
めんどくさそうな人柄を察知した鶴屋、
「よかったじゃないですか蔦屋さん。作者が見つかって」
笑顔で押し付けて去る素早い判断力に笑ってしまう。
というか、京伝も押しかけ弟子の瑣吉の扱いに困っていたらしい。
逃げそびれた蔦重は、作家見習い兼手代として瑣吉を耕書堂に置くことにした。
瑣吉の生まれ育ちは町人ではない。さる旗本に仕える武士だった父は、幼い頃に世を去った。それからずっと不安定な生活を送っていたのである。
手代として働き始めたのに、態度がデカいのなんの。
へらず口を叩く瑣吉に、手代・みの吉(中川翼)が苛立つ。
みの吉「働け! 老け顔!」
瑣吉「まあ、そう妬むな。童(わらべ)顔」
新人スタッフのくせにチーフに暴言。こんな従業員はいやだ。
一応作家見習いなので、蔦重は原稿を書かせてみた。それを一読した絵師・北尾重政(橋本淳)は「随分と独りよがりだねえ!」と笑った。
それに頷きながらも蔦重は「けど細かく読んでくと面白えとこもあるんですよ」と評価する。その目はやはり名編集者、名プロデューサーというべきか。
そこへ、絵師・勝川春章(前野朋哉)が弟子の勝川春朗(くっきー!)を伴ってやってきた。
38話(記事はこちら)で重政が「揉め事ばかり起こしているが先の読めないやつ」と言っていた男だ。
のっそりと蔦重の前に腰をおろした春朗、唐突に、
春朗「たらーりたらーり。たーりらーりらーん」
春章「ちょいと言葉が変わってるんだよ。水も滴る男前って言いたいんだよ」
オリジナリティあふれる言葉遣い……慣れた様子で訳してみせる春章先生、さすが懐が深い。
蔦重は、瑣吉の黄表紙に春朗の挿絵をと考えて組ませようとする。だが、癖が強すぎる作家と絵師が出会って、何も起こらない筈がない。
たちまち喧嘩となった。
耕書堂前の往来で取っ組み合いを始めるふたり、盛り上がる野次馬。
ナレーション「滝沢瑣吉のちの曲亭馬琴」「のちの勝川春朗のちの葛飾北斎」
曲亭馬琴と葛飾北斎。ふたりはこの先も仲良く喧嘩しながらタッグを組み、数々の名作を生んでゆく。『椿説弓張月(ちんせつゆみはりづき)』などコンビでの作品群、また、曲亭馬琴『南総里見八犬伝』、葛飾北斎『富嶽三十六景』などそれぞれの代表作は、小説、漫画、映画、アニメ……現在に至るまで多くのエンターテイメントの素地となっているのはご承知の通り。
その萌芽は蔦重の、耕書堂で育まれたのだ。
まこと良い流れではあるが……
未来の大ヒット作はともかく、現在の大衆向け出版情勢は苦しい。
黄表紙も狂歌も錦絵も、幕府の圧力のせいで勢いがすっかり落ちてしまっているのだ。
黄表紙に教訓本が取って代わり、バカバカしかった狂歌は格調高くなり、錦絵は相撲絵、武者絵が幅を利かせ、煌びやかな女郎の絵などは影を潜めてしまった。
所変わって、老中首座・松平定信(井上祐貴)の屋敷。
水野為長(園田祥太)「新作の点数はぐっと減りましてございます」「殿の望み通りの流れになってきておりますよ」
定信の前に、今年出版された錦絵と黄表紙をずらりと並べて、水野は喜ばしいこととして報告する。
耕書堂から出た新作黄表紙をに目を通しつつ眉根を寄せていた定信。相撲絵、武者絵など無骨一辺倒の錦絵の並びを見渡し、思わず呟く。
定信「まこと良い流れではあるが……」
水野「が?」
定信「……いや。良い流れである」
自ら命じた苛烈な出版統制だ。
今更、世に出ているものが全部つまらん、面白くないなどと言えようか。良い流れだと言葉を改めたものの、錦絵を眺める定信の眉根は寄ったままだった。
同じころ、耕書堂でも蔦重が錦絵を並べて眺めていた。
相撲取り、歌舞伎の立役(男役)、軍記物の武者──むくつけき男ばかりの絵の上に、喜多川歌麿(染谷将太)が描いた亡き妻・きよ(藤間爽子)の絵を重ねてみる。
多色刷りの鮮やかな錦絵の中にあって、際立つ墨一色の存在感。
蔦重「今、女絵を出せば間違いなく目を引く。それに、この大きさ。女の大首絵なんて見たことないだろ」
てい(橋本愛)「大首絵……」
大首絵とは、上半身を大きくクローズアップして描いた絵のこと。それまでは主に歌舞伎役者がモデルであった。ファンが買い求めるブロマイドのようなものだ。
なので、ていは「役者絵ならまだしも、女絵で成り立つのでしょうか」と疑問を呈する。
蔦重「女の顔はみな同じに描くし表情もねえ。それを大きくしたって面白くもねえ」「だが今の歌麿なら表情も出せる、女の描き分けができる。つまり、女の大首絵が描ける」
「喜多川歌麿は当代イチの絵師になる」
だが、歌麿が引き受けてくれるかどうか。蔦重と歌麿の間には、きよの臨終の際に生じたわだかまりがある。それを超えて描いてもらうには、案思(アイデア)しかないと蔦重は言う。作家に書きたい、描きたいと思わせるアイデアを持ってゆくのだ。
これまでの経験で、蔦重はそう確信する。
巷の美人を訪ねて
歌麿に働きかける前に、まず案思。
市中の美人巡りをする蔦重。江戸の女のことなら俺に任せろとでも胸を叩いたのか、案内は瑣吉だ。
その案内の先に、出たっ!
浅草随神門脇の難波屋おきた(椿)、両国薬研堀の高島屋おひさ(汐見まとい)!
浮世絵史上に燦然と輝くその名前。
彼女たちは実在した美人と評判の看板娘である。おきたが働く茶屋の客は見事に男性ばかり。おひさの煎餅屋も並んでいる8割は男性だ。
ふたりとも水茶屋で働く女性だったという。高島屋おひさは父が煎餅屋と水茶屋を兼業し、どちらも手伝っていたのだとか。茶屋に娘を置く水茶屋は他の茶屋よりもお茶代が高く設定されており、現代のガールズバーに近い感覚だったのではないだろうか。
熱心に通い詰める男性客が多く、会いに行ける推し娘だった。
蔦重「今は巷の美人に男が群がるんだな」
瑣吉「不景気で皆、吉原など高くて行けぬ。その点、巷の美人はタダで見られる」
なるほどねえ……しかし彼女たちも商売だから、金を払わずに入り浸る客は迷惑だろう。馴れ馴れしく距離を詰めてくる瑣吉がおきたにもおひさにも鬱陶しがられているのは、金を落とさないからか、強すぎる圧のせいか。
「巷の美人を描く」というだけでは、歌麿を説得する案思にはならない。あともう一押しほしい。
耕書堂に戻ると、義兄の次郎兵衛(中村蒼)が訪ねてきていた。
次郎兵衛は『相法(そうほう※人相学)』の本を片手に、ていと遊んでいる。
吉原では今、人相・顔相が流行りはじめているという。血液型占いに手相占い。今も昔も、
酒席での座興には占いが人気。
「これだ!」蔦重が閃く。
釜屋伊兵衛にも共感
歌麿は、栃木の豪商・釜屋伊兵衛(益子卓郎)の屋敷に身を寄せていた。
その静かな環境は、鳥山石燕(片岡鶴太郎)に弟子入りしていた頃のようだ。
同行している蔦重の母・つよ(高岡早紀)との穏やかな会話は、母子のそれに見える。
つよとの生活は歌麿を癒しているのだろう。そして、つよも歌麿を息子のように可愛がることで、心に空いた穴を埋めているのではないかと想像するのだ。
話が横に逸れるが、39話(記事はこちら)で「歌麿とちゃんと話さねえと」という蔦重を「そりゃ自分のためだろう。自分の気持ちをわかってほしいだけだろう」と止めたことが気になっている。
つよが幼い蔦重を捨てて男と逃げたというのは、噂話に過ぎない。
だが、事情があって胸引き裂かれるような思いで我が子と別れたのだとしても、置き去りにしたことには変わりない。つよは「自分の気持ちをわかってほしいだけ」の言い訳めいた話を、蔦重にすることを控えているのではないだろうか。
江戸から蔦重が訪ねてきた。
「お前は鬼の子なんだ、生き残って命を描くんだ」
蔦重の言葉(38話)に深い心の傷を負った歌麿は、応対はするものの、よそよそしい。
蔦重は「鬼の子」の言葉を謝罪した上で「錦絵を出してほしい」と頭を下げた。
蔦重「俺は、喜多川歌麿先生にこんなものを描いてほしいんでさ」
広げて見せたのは、きよを描いた絵に『婦人相学十躰・清らかなる相』とタイトルをつけたもの。
大流行の兆しを見せる「相学」になぞらえて、様々な女の相を描く。
それができるのは、女を繊細に描き分け、魅力的な一瞬を捉えることができる絵師──喜多川歌麿しかいない。
「お願いします」と頼み込む蔦重、「もう女は描かないと決めた、おきよは自分だけを見てほしいと願っていたから」と断る歌麿。
蔦重「そりゃ、生きてる間はってことだけだよ」
歌麿「蔦重はおきよのことなんて何も知らねえだろ!」
蔦重「知らねえよ。けど、この世で一番好きな絵師は同じだからよ」
「お前の絵が好きな奴はお前が描けなくなることを望まねえ」
歌麿の傍には、当主・釜屋伊兵衛が控えている。歌麿の絵に惚れ込み、肉筆画を請うて屋敷に招いた伊兵衛が、蔦重の言葉にただ頷く姿に目を惹かれた。
ファンは作家の心身の健康を願いながら、新たな作品を待ち望むものだ。
この場面は蔦重の言葉と同じくらい、釜屋伊兵衛の姿に共感した。
蔦重「きよはきっと、草葉の陰で絵師・歌麿のモデルになったことを自慢している」
蔦重は、選択を委ねる。
「お前が俺とこれをやりたいか、やりたくないか。それだけで決めてくれ」
歌麿は受け入れた。
小道具を使う美女
江戸に戻ってきた歌麿は、『婦人相学十躰』制作に取り掛かった。
蔦重がスカウトしてきた巷の美人たちを、とにかく写して写して写しまくる。
一人一人の女性を忠実に写しとった絵に蔦重は、
「ここまで真に迫ってほしいわけじゃなくて、あくまで女絵として綺麗であってほしいんだ」
蔦重の注文に「そんなこと言ってなかったろ」と文句を言いつつ、歌麿は女絵の研究をする。
目、鼻、口。写実的な女の顔のパーツ。そこから一歩進めて、どこにでもいるようでいて、どこにも存在しない美女を生み出す。
このあたり、なんとなくだが別の絵師の存在を思い浮かべてしまった。
真に迫った姿。綺麗とは言えない、人間としてのリアリティ。ここから連想するのは、まだ登場していない超有名絵師だ。もしかして?
ポーズを決めるにも余念がない。
蔦重は、きよの絵姿には想像力を働かせるものがあると褒めた。これこそが、役者でも女郎でもない、市井に生きる女性の絵を買わせる魅力になるのだと。
その言葉に歌麿は、女に煙管や手鏡、ポッピンなど小道具を使うことを思いつく。小道具を使う仕草には性格が出る、美女のポーズに想像の余地が生まれ、物語性が膨らむ。これは「相学」を謳うにはうってつけだ。
この場面、歌麿が煙管を吸う蔦重に見惚れる表情が印象的である。
きよのことを忘れたわけではない。愛している。でも──。
人間の愛とは、どうしてこうも複雑なのだろう。
京伝リサイタル
歌麿は絵師として江戸に戻ってきた。
残る課題は、京伝の執筆復帰問題。
絵師、戯作者を引退するにあたり、煙草入れの店を始めると言い出した京伝は、そのスタートアップ資金を調達するため、書画会を開きたいと鶴屋に協力を求めた。それを聞いて、ニヤリとする蔦重と頷く鶴屋。
ふたりの地本問屋の頭の中に、京伝復活への道筋が描かれる。
書画会当日。料亭の広間にやってきた京伝が浴びたのは、集まった京伝ファンによるモテの熱いスコールだった。
「きゃー!! 京伝先生!!」「よっ!! 京伝先生!!」「日本一!! 色男!!」
テンションが花火のようにぶちあがる京伝。
もともとモテたくて絵師・戯作者をやっていた男なのだから、気をよくして当然だ。
京伝の妻・お菊(望海風斗)が三味線を奏で始める。
京伝ファンが「『すがほ(素貌)』だ!」と歓声を上げた。作詞・山東京伝のめりやす(芝居の挿入歌)だ。京伝が歌い始める。
「文のさきめの口紅も外へ移さぬ心とは、神々さんもどこやらも、とうに承知であろけれど……」
身請けされることが決まった女郎が、女郎としての化粧を落として愛しい人に素顔を見せる日を心待ちにする、抒情的な歌である。めりやすは芝居の挿入歌、まるでミュージカルのワンシーンのようだ。
素晴らしい美声! 京伝リサイタルにファンはますます盛り上がる。
黄表紙にサインを頼む若者・太輔(荒井雄斗)は、のちに滑稽本『浮世風呂』(文化6年/1809年~文化10年/1813年)などを執筆して大人気作家となる式亭三馬(しきていさんば)。
持ってきた黄表紙『江戸生艶気樺焼(えどうまれうわきのかばやき)』は愛読書なのだろう。京伝作品で育った若者が大衆に愛される次世代の作家になることを示す場面だ。
気分よくサラサラと艶二郎(えんじろう/『江戸生艶気樺焼』の主人公)の絵もつけてサインする京伝、鶴屋がファンに白扇を配ったので我も我もと山東京伝先生サイン会会場に早変わり。
京伝にとって熱いファンの声ほど嬉しいものはないだろう。その声を直接大量に浴びたのだから、京伝は引退を翻し、絵師も戯作も続けることにした。
蔦重と鶴屋の作戦は大成功だ。
モテてえ欲、描きてえ欲
復帰のいきさつを京伝から聞いた歌麿、
「煙草入れ屋と二足の草鞋で行くことにしたの?」
京伝「本屋はくすぐるのがうまくて嫌になるよ。けど、それにやられちまうのは自分の中に欲があるからなんだよな。モテてえ欲、描きてえ欲。歌さんはどうだい?」
歌麿「欲なんて、とうに消えたと思ってたんだけどなあ……」
欲望は人の命を燃やす炎。欲があるからこそ、前に進むことができる。
歌麿は自分を絵の道に引き戻した欲──その源泉を静かに見つめている。
次回予告。
「書を以て世を耕す」。須原屋さんお元気そうです。一橋治済(生田斗真)また江戸市中に出てきてる。行列に並び笠を被った姿で蔦重を見ている。見るな触るな近づくな。 おていちゃん、なにが無理なんです? 歌麿の美人絵が世に出る。つよさんが、蔦重をこの名前で呼ぶのは初めてではないか……「からまる」。
41話が楽しみですね。
*******************
NHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』
脚本:森下佳子
制作統括:藤並英樹、石村将太
演出:大原拓、深川貴志、小谷高義、新田真三、大嶋慧介
出演:横浜流星、生田斗真、染谷将太、橋本愛、古川雄大、井上祐貴 他
プロデューサー:松田恭典、藤原敬久、積田有希
音楽:ジョン・グラム
語り:綾瀬はるか
*このレビューは、ドラマの設定をもとに記述しています。
*******************