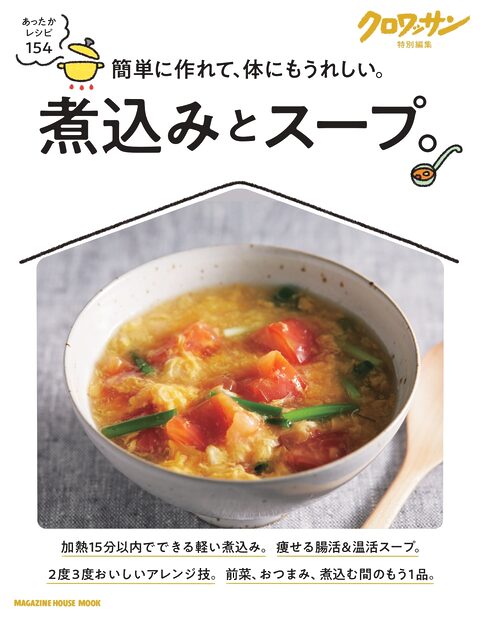考察『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』31話 将軍家治(眞島秀和)死す、ふく(小野花梨)の悲劇に絶句…蔦重(横浜流星)は米の差し入れをせねばよかったのか
文・ぬえ イラスト・南天 編集・アライユキコ
待たせたな、市中!

31話で描かれたのは、この世の地獄であった。
天明6年(1786年)利根川決壊。「天明ノ大洪水」が起こる。将軍・家治(眞島秀和)と田沼意次(渡辺謙)ら幕閣は江戸の民衆を救うべく動くが、事態は思わぬほう、悪いほうへと転がってゆく。
蔦重(横浜流星)の耕書堂で食事する山東京伝(古川雄大)と唐来三和(山口森広)が飛ばす冗談と、「待たせたな、市中!」と張り切る長谷川平蔵(中村隼人)くらいしか和むポイントがない。
もっとも、京伝らが受け取る茶碗の飯は以前のように大盛りではなく、天下の日本橋の商家ですら食料に窮する現状が伝わる。耕書堂に集う面々は明るく振舞うが、その内実はやるせない。
こうなったら頼みは平蔵のトンチキぶりだが、現在彼はどうなっているのだ。
ひさびさに登場した平蔵は、被災者への配給の行列の様子を窺っていた。蔦重はそれを見つけて声をかける。答えて平蔵、
「御先手弓頭(おさきてゆみがしら)になってな。次はいよいよ奉行かってことでな」
平蔵が、次はいよいよと昇進を期待する町奉行は、警視総監・裁判長・都知事をあわせたような役職だ。平蔵のように旗本という家柄の者が就けるうちでは、最高の上級文官である。
対して現在の官職──御先手弓頭は、将軍が江戸城から出る際の警護と、治安維持のために与力・同心といった実働部隊を率いる武官だ。
平蔵、天明6年で40歳、蔦重は36歳。第1話(記事はこちら)でふたりが出会ったのは安永2年(1773年)、あれから13年経ったわけだ。ふたりともすっかりいい大人になった。
ただ平蔵は、若いおなごの視線を意識して「こうして日夜、市中を見回ってんのさ」とカッコつけるあたり、イキリ散らした青年だった頃と変わっていない。
平蔵の子分である磯八(山口祥行)と仙太(岩男海史)、昔と変わらず「兄ィ」と慕っている。「向こうで喧嘩だ」と聞くやいなや、配給の列を尻目に勇んで駆けてゆく平蔵。行政の長である町奉行よりも、こうした事件性のある現場が似合うのではなかろうか。
思えばこのとき、平蔵が蔦重に掛けた「盗みや押し込みが増えておるゆえ、なにかあったらすぐに申せ」という忠告は、ドラマ後半への伏線であった。
間の悪い貸金会所令
天明の大飢饉が収束しきっておらず、幕府には江戸市中に食料を行き渡らせる余力がない。物価の高騰も天井知らず。
平蔵の「もはや裕福な町方の助けが頼りだ」の言葉を受け、蔦重は日本橋通油町の商人仲間に江戸町民救済を提案するが、賛同する者はいない。
蔦重「どっかから金が降ってきませんかね」
鶴屋喜右衛門(風間俊介)「どうやら、お上もそう思っているようですよ」
鶴屋が述べたのは、田沼意次主導で発令された貸金会所令(かしきんかいしょれい)についてだ。
天明の大飢饉により、領民の救済に追われた全国各地の藩の財政は火の車だった。幕府が諸大名に融資する資金を全国から集めようとしたのが、この貸金会所令である。
寺社からは最高15両(現代に換算しておよそ150万円以上)、百姓からは米の在庫100石(1石がおよそ1,000合)につき銀25匁(およそ57,000円)、家屋敷を所持する町人からは間口1間あたり銀3匁(およそ6,750円)を、天明6年から向こう5年間、毎年徴収するという法律だった。
融資なので、5年後に年利約7%の利息がついて戻ってくる。今に例えるならば、国債に似た仕組みだろうか。時代を先取りした政策であり、上手くゆけば評価されたのだろうが、発布直後に大洪水が起こってしまった。ナレーションのとおり、
「なんとも間の悪いことに、大水の直後に知れ渡ることとなったのです」。
先だっての鶴屋の苦々し気な口ぶりは、利息付で返済されるメリットよりも、徴収されるデメリットを問題視するものだった。そう感じたのは鶴屋だけではない。江戸城内では融資される側の大名たちが、松平定信(井上祐貴)を筆頭に「飢饉と洪水で困窮している民から金を借りるなど、末代までの恥さらし」と法令撤回の声を上げる。洪水の後始末に追われる町人の間では「俺たちに出せってんですかい、大名に貸すための金を」「血も涙もないのかい」と大不評だ。
もともと下地としてあった田沼政治への批判が、更に強まることになってしまった。なおのこと庶民は理解も納得もしていない。
ひとに身を差し出すのは慣れているから
蔦重は、新之助(井之脇海)ふく(小野花梨)夫婦に説明する。
融資した金は利息付返済されること、新之助たちのように自分の家屋敷を持たない長屋住まいの人々からは徴収されず、長屋の家主が支払うことなど。
蔦重の紹介で、夫婦は深川の長屋に身を寄せていて、蔦重は米などの差し入れに訪ねてきたのだ。
「そのへんも(民のことを)ちゃんと考えられてる」と、笑顔で頷く蔦重。それを我が子・とよ坊に乳をやりながら聞いていたふくが「蔦重はあいかわらず田沼びいきだね」と静かに語り出した。
「家主は金を出せと言われれば家賃を上げるさ。米屋は米の値を上げるし」「吉原では、女郎からの取り分を増やすだろうね。ツケを回されるのは私ら、地べたを這いつくばってる奴。それが私が見てきた、浮世ってやつなんだよ」
融資と言っても、任意ではなく強制徴収である。取られた側は価格を上げて補おうとするだろう。よって物価はさらに上がってしまい、苦しみは増してしまう。はなから百姓でも商人でもない庶民に利息が戻ってくることはない。
なによりも皆、5年先などとても考えられない。今日明日を生きるのに精いっぱいである。
返す言葉もない蔦重。
そこへ、空腹に泣く赤子を抱えた母親たちがもらい乳にやってきた。満足に食べられず、乳の出なくなった女性たち。身なりからして長屋の住人ではなく、洪水で家を失った被災者か流民だろう。ふくは蔦重の差し入れのおかげでかろうじて乳が出るので、よその赤子に飲ませているのだ。新之助の「『私はひとに身を差し出すのは慣れているから』と言ってな」という台詞に、ふくが女郎だった過去が思い起こされる。
「困ったときは、お互い様ですから」と乳をやる。ふくの穏やかな笑みが菩薩のようだ。
真夏の手作り醍醐
江戸の町民らが人を思いやり、食べ物を分け合っているこの時。江戸城内でも、思いやりから食べ物を差し入れている人物がいた。
10代将軍・家治(眞島秀和)の体調不良を耳にした将軍側室・知保の方(高梨臨)は「何か滋養のあるものをお見舞い申し上げたい」と、家斉の乳母であった(詳しくは後述)御年寄・大崎(映美くらら)に相談する。大崎が提案したのは、醍醐(だいご)だ。醍醐とは牛乳を加工して作られる食品だが、製法は現代では不明である。形状はヨーグルト、あるいはチーズのようなものではないかなど、諸説ある。古来より最上の味、口にすれば諸病を除くとされた食べ物で、「醍醐味」の語源ともなっている。
知保の方は手作りした醍醐を持って家治を見舞った。
冷蔵庫のない時代の真夏に、作ってからどれだけ時間が経ったか不明である素人のお手製乳製品だ。それだけでも食中毒を起こすのではと怯えてしまうのだが、家治は側室の心づくしを喜んだ。しかし、知保の方が「醍醐はかつて田安家が将軍家に納めていたと聞き、越中守様(松平定信)に作り方を教わりました」と伝えた瞬間、家治の顔色が変わる。
松平定信は将軍から田安徳川家を継ぐ許しを得られず、白河松平家に養子に出ることになってしまった。家治に恨みを持っている可能性はゼロではない。
醍醐を食すことを躊躇する家治に、傍に控えていた大崎が、
「田安は取り潰しが決まっております。なにとぞ、ひと口だけでもと、越中守様も仰せにございました」
これが田安徳川家から将軍に献上される最後の醍醐になるかもしれない。と口添えしたのだ。
自分を気遣ってくれる知保の方の気持ちと、取り潰される家の矜持。夫として将軍として、いずれも無下にしがたく、押し返さないのが温厚な家治らしい。
家治は毒見を申し付け、その場で醍醐を口にすることとなった。
大崎という女性
はたして、将軍・家治は病に臥せった。
しばらくその事実は隠され、将軍と大名が謁見する月3回の定例行事・月次御礼(つきなみおんれい)に家治は姿を見せない。貸金会所令の撤回を、直接将軍に訴えようと準備していた松平定信は田沼意次の謀り事かと疑ったが、老中席にいる意次の様子を窺い、「あちら(意次)も予期せぬことか」と思い直した。このあたり、頭ガチゴチに見えて視野が狭いわけではないらしい、定信の性格が現れている。
将軍 御側御用取次役・稲葉正明(木全隆浩)は、意次だけに将軍の状態を耳打ちした。
毒見役らに異常はない、家治のみが腹痛を訴えているという。医師の見立ては、体調不良に食べつけぬものを口にしたせいではないかということだったが、家治自身はそう捉えなかった。
知保の方と松平定信。このふたりに毒を盛った疑いがかかるよう仕組んだ者がいる。家治は意次にそう指摘する。それを仕組んだ人物── 一橋治済(生田斗真)に思い当たり、治済の名を出さず問う意次。「あの者の考えていることがわかりませぬ」。
家治「あやつは天になりたいのよ。あやつは人の命運を操り、将軍の座を決する天になりたいのだ」「将軍の控えに生まれついた、あの者なりの復讐であるのかもしれんな」
なにがしたいのか、これまで見当もつかなかった黒幕・治済の意図について、ここで推測ではあるが語られた。男子を作り、将軍家に差し出す役割しか与えられていない家(御三卿)に生まれた男の社会への復讐を、徳川将軍家に生まれ、将軍という座から逃れたくても逃れられない家治だけが理解できる構図だった。
家治は己の不調を毒だと確信している。解毒が得意な医師を派遣するよう、意次に命じた。
一方、家治が病だと知った知保の方は「まさか私が食べ慣れぬものを差し上げたせいではあるまいな」と狼狽えていた。大崎は知保の方に固く口留めした上で「大事のうございます。私がお守りしますゆえ」と慰めるのだが、寄り添うその目は冷たく光っている。
この大崎という女性について触れておこう。以前は一橋家で治済の長子・豊千代の乳母として仕え、今は江戸城大奥で御年寄(奥女中の中でも上級の役職)だ。
知保の方は家治の嫡男・家基(奥智哉)の死後、大奥を出て江戸城二の丸御殿に住んでいる。ひっそりと暮らしている知保の方のもとに足しげく通い、懐柔していったようだ。
30話(記事はこちら)で家治は「近頃、知保と将棋を指しておる」と言っていた。二の丸御殿を訪れ、知保の方と将棋を介して亡き息子を偲んでいたのだ。そこではお茶や菓子が出ただろう。大崎は二の丸で少しずつ家治に毒を盛るよう謀っていたのではないだろうか。
毒は体内に蓄積されていき、もう一服盛れば致命的な打撃を与えるまでになったとき、最後の一押しが醍醐に仕込まれた毒だったのではないか。
ドラマでははっきりと描かれていないので、勝手な憶測である。
だが、大崎は治済の実子で次の将軍である家斉(長尾翼)の乳母だ。その昔、3代将軍・家光の乳母・春日局という、絶大な権勢を奮った女性がいた。そうした座を狙って動いているのだとすれば、大崎は治済の手駒というより、陰謀の主犯格である。
松平康福の一喝
家治の病は隠しておけないほどに重くなった。意次が将軍に毒を盛った噂まで流れるなか、老中首座・松平康福(やすよし/相島一之)が呟く。
「土産を考えたほうがよいかもしれんな。土産がなくば、我らも一蓮托生となろう」
松平康福は、娘を意次の亡き嫡男・意知(宮沢氷魚)に嫁がせている。もう一人の老中、水野忠友(小松和重)は意次の四男を養子としていた。どこから見てもドップリ田沼派であるふたりは迫り来る田沼派粛清の嵐を免れるため、寝返りを画策して土産を用意した。
それは、意次の登城差し止め。表向きの理由は、意次が派遣した医師の治療により将軍の容態が悪化した責任を問うものだった。憤る意次を康福が一喝する。
「そなたのために言うておる! 自ら退いた方が、家名も禄も守れよう。このままでは全てを失いかねぬぞ」
これまで、風見鶏のような頼りなさで、時にコミカルにまで感じられた松平康福。相島一之の怪演で、生き残る術に異様に長けた幕臣の顔が現れた。怪物は一橋治済だけではない、江戸城は魑魅魍魎の巣窟なのだ。
将軍・家治が倒れた今、意次はその巣に近づくことすらできない。将軍の容態も教えてもらえぬまま、意次は老中職を辞した。できることはただ、家治の回復を祈るのみ。
天は見ておるぞ
瀕死の床で、家治は家斉に言い遺す。
「田沼意次は『まとうどの者(正直者)』である……臣下には正直なものを重用せよ。正直な者は、世のありのままを口にする。それが我らにとり不都合なことでも。政においてそれはひどく大事なことだ」
政治を司る者にとって、不都合なことであろうと率直に伝える、世に知らしめる。
その大切さを説くこの台詞は、本作のこれからの展開にも、現代を生きる我々の社会にとっても普遍的な、重要な言葉だ。
ここから家治は、最後の力を振り絞った。「家基、家基」と亡き息子の名を呼び、末期の幻を見ているように振る舞いながら、治済に「家基を暗殺したのはお前だろう、わかっているのだぞ」と伝える姿は鬼気迫る。治済の胸倉を掴み、
「よいか……天は見ておるぞ。天は天の名を騙る奢りを許さぬ。これからは余も天の一部となる。余も見ておることをゆめゆめ忘れるな」
この回のサブタイトルは「我が名は天」。将軍家を手中に収めようとしている治済のことかと思ったが、家治の最期の誓いでもあったとは。序盤の治済の「天は見ておられようぞ。正しき者は誰か」という言葉が、これからブーメランとなって治済に突き刺さるのか。
突き刺さってくれ、頼むから。
10代将軍・家治の死。それを誰からも知らされることなく、自分の屋敷の縁側で独り将棋を指す意次……ふと盤上の向こうを見て微笑むその目には、長年の戦友・家治の姿が見えているかのようだった。
小さな死
ナレーション「世の節目となる、大きな死。その一方、市中の片隅の小さな、小さな死」
新之助と同じく「えっ……え?」と声が出た。なんで!? とも叫んでしまった。家に帰った新之助が筵(むしろ)をめくると、ふくの遺骸。その隣に並んだ、小さなとよ坊の遺体を見た時はもっと大きな悲鳴が出た。なぜ、こんなことに。
目に入ったのは、乱暴に荒らされた箪笥と行李、引き出された衣類。
強盗か……。
犯人はすぐに捕まった。血の付いた米袋を前に土下座して泣きわめき謝罪する下手人の男。その隣で赤子を抱え「私があの家には米があるんじゃないかって言っちまったもんで」と泣くのは、ふくにもらい乳をした流民の女だ。
ふくだけ他人の子に分けられるほど乳が出ているのは、人よりも多く食べているからではないかと夫婦の会話に上ったのだろう。洪水の直後なのに、とよ坊に着替えがあることから、時折現れる立派な身なりの男──蔦重が差し入れていると察したのだ。
ひもじさがもたらす羨みと妬みとが、もらい乳の感謝を上回ってしまった。
何故とよ坊まで……茫然としたが、流民の女が抱く赤子の、耳をつんざくような泣き声で気づいた。ふくが斃れた直後、とよ坊が激しく泣いたのか。隣近所とのつきあいが密な長屋である。誰かが様子を見に来るかもしれないと焦り、赤子を手にかけてしまったのか。
魔が差したとはこのことだろうが、それにしても非道だ。
新之助「この者は俺ではないか」「俺はどこの誰に向かって怒ればいいのだ!」
江戸時代、殺人は死罪である。夫が罪人として処されたら、残された妻子の未来は暗いだろう。咎人の妻子を保護する者は誰もおらず、生きてはゆけない。新之助が怒りを押し殺しても、誰一人救われないのだ。
食べるものがなく乳の出ない妻と、腹を空かせて泣く我が子。あの家に米があるのではと耳にしたら、自分も同じことをしたのではないかと、聡明な新之助は瞬時に思い至ってしまう。一歩間違えれば自分とて……という暮らしを、これまで経験してきたのだ。12話の『明月余情』(安永6年/1777年)、俄祭の駆け落ち(記事はこちら)から9年。苦楽を共にした夫婦がこんな結末を迎えるとは、誰が予想しただろう。
俺はもはや逃げてはならぬ
どうしてこうなった。
蔦重が新之助夫婦に差し入れをせねばよかったのか。ふくが、よその子に乳を与えねばよかったのか。知保が伴侶の健康を願って見舞わねばよかったのか。
誰かのためになりたいと行動した人間は、悲劇を呼んでしまうものなのか。
いや、そうではない。そんなわけねえだろ。それが世の常だなんて、絶対に否定するぞ。
14話(記事はこちら)の瀬川(小芝風花)の言葉が蘇る。
「巡る因果は恨みじゃなくて恩がいい」
恩が恩を生んでいく世にするのは、一体どうすればいいのだ。
「俺はもはや逃げてはならぬ気がする」
ふく、とよ坊を葬った新之助が何ごとか決意して語った。無数の土饅頭(墓)を前にした蔦重、その目が向けられた天は鈍色の雲に厚く、重く覆われている。
次週予告。「我々、打ち壊すべし」。天明の打ちこわし勃発。新之助の怒りは幕府に向けられた。名のない男(矢野聖人)の横にいる流民は治済!? もしそうなら何してんの。
大田南畝(桐谷健太)、朋誠堂喜三二(尾美としのり)、恋川春町(岡山天音)ら戯作者集結。あっ! 次回は次郎兵衛(中村蒼)が出る! よかった、この重苦しさは兄さんが出ないとなんともならない!
32話が楽しみですね。
*******************
NHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』
公式ホームページ
脚本:森下佳子
制作統括:藤並英樹、石村将太
演出:大原拓、深川貴志、小谷高義、新田真三、大嶋慧介
出演:横浜流星、生田斗真、渡辺謙、染谷将太、橋本愛、岡山天音 他
プロデューサー:松田恭典、藤原敬久、積田有希
音楽:ジョン・グラム
語り:綾瀬はるか
*このレビューは、ドラマの設定をもとに記述しています。
*******************