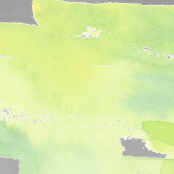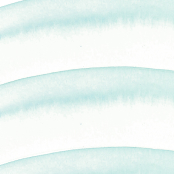『木皿食堂3 お布団はタイムマシーン』著者、木皿 泉さんインタビュー「正直なことを書くと、共感されるんですよ。」

撮影・清水朝子
脚本家の木皿泉さんのエッセイは、名言の宝庫だ。話の始まりはごく日常の風景なのに、それまで意識していなかったけれど深く共感するフレーズや、そういうふうに生きたいと同意せずにいられない一言に導かれ、毎度心を動かされてしまう。“イヤミなことを言われたと憤慨するのは、相手の悪意を受け取っている、親切な行為である”ということだったり、“自己責任ばかり言われ続けている私たちは、ときどき自分より大きなものに大丈夫と言ってもらいたくなる”“惨めかどうか決めるのは私自身で、他人は私を汚すことはできない”ということだったり。
「きっとね、自分を救うために書いているような気がします。世間には非常識と思われるような考えでも、わが身を守るためにはいいんじゃない? 自分が苦しい時に書いていることが、お言葉みたいになっているのかもしれませんね。発明みたいなものでもあるのかな。くよくよしないでも、こういう考え方があるよという」
とは、木皿泉さんのかたわれ、妻の年季子さん。子どもの頃の話も鮮明に描かれ、その記憶力には驚かされる。文字を読んでいるのに、シーンが映像で浮かぶのだ。
「誰が何をしていたか、けっこうしっかり映像で記憶しています。目の前に映像的なものが見えないと、短いエッセイも書けないくらい」
同時に、“君は僕のクリーンヒットや”とか“どこにいても私らしくいられるのは、私の好きな彼のおかげ”など、夫との愛を感じるエピソードには心温まる。毎日延々と会話するので、どれがどちらの考えとの区別もなく書き進められるが、行き詰まった時のヒントは夫の得意分野。“お金がみかんみたいに腐るものだったら、腐らないうちに人に配ることができる”という名言を含む〈みかんとゾンビ〉の逸話に、ゾンビを提示したのも夫だ。
「ゾンビ映画の録画があると言われて30分くらい観たらピタッと文章も着地できた。たまたま家にあった腐ったみかんともつながって。もう、ぜんぶ撮って出しです。そこらへんのもので、という感じ。でも、そのほうがいいんですよね」
自分にとって本当のことが、みんなにとっても本当のことなのが、不思議な感覚だと、年季子さん。
「私に固有のことを書けば書くほど、みんなが共感してくれるんですよ。自分の中に近づけば近づくほど、みんなに近いって、どういうことですかね?」
みんなが感じている言葉にならないもやもやを、まっすぐに代弁してくれるからではないだろうか。

双葉社 1,400円
『クロワッサン』971号より