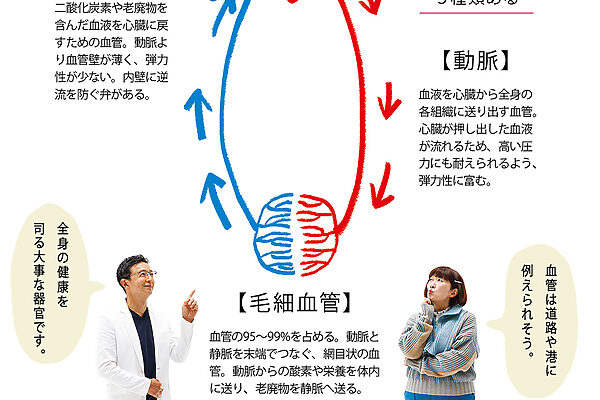『性食考』赤坂憲雄さん|本を読んで、会いたくなって。
人間の、根源的な二つの行為を想う。

撮影・尾嶝 太
「この頃ボクは文ちゃんがお菓子なら頭から食べてしまひたい位可愛いい気がします」
芥川龍之介がのちの妻に宛てた恋文から始まる本書のテーマは「食べる」ことと「交わる」こと。岩波書店のwebで「歴史と民俗のあいだ」という連載を始めたとき、まさかこんな展開になるとは想像していませんでしたと、赤坂憲雄さん。
「僕、書く前にメモを作ったり全体の構想を練ったりしないんです。手探りで書き始めて、粘土をこねるように思考を重ねるうちに考える土台ができてくるんです」
最初に異類婚姻譚を取り上げたとき、奇妙に「食べる」「交わる」といったテーマが顔を現した。資料に当たると、両者を個別に論じたものはあっても性と食の交差するところを扱ったものはない。
「誰もやっていないのなら、自分でやってみようか。手繰り寄せるように資料を集め始めました」
性食と書いて、〈せいしょく〉と読む。性と食のあいだに存在する親和性に、誰もがうすうす気づいていながら表立って論じる者はいなかった。なぜだろう。
「食べることも交わることも、人間にとって根源的な、いちばん基本的な行為。とても大切で厳粛なものであると同時に、タブーの観念にも関わってきます」
じつは赤坂さん自身、今までの著作のなかで、性について書いたことは一度もないのだという。
「書いていて自分がとんでもない世界に入り込んでいく予感がありました。これは中途半端にやるとかえって卑猥になってしまう、容赦なくやろうと覚悟を決めました」
絵本から民話や昔話、そして神話へと赤坂さんの思索は、広がっていく。たとえば男女の性的な関係を食べることに例える習慣から、聖アウグスティヌスの「私たちは糞と尿のあいだから生まれるのだ」という言葉まで幅広く奥深く。
「食べる・交わる場面で、私たちはいやおうなしに内なる野生、動物性というものに向き合わざるをえません。でもそれは特別なことじゃなく、芥川の手紙のように、ごくふつうの人たちにとって日常の、当たり前のことなんですね」
赤坂さんの語りは噛みしめるようにていねいだ。聞けばパソコンも、両手の人差し指だけを使う「ひらがな変換一本打ち」なのだという。そんな書き手のペースにあわせてゆっくりと味わいながら読む。眠っていた記憶が掘り起こされ、想像が翼を広げる。読書って人間を豊かにしてくれるものだな、そう思わせてくれる久々の本。

岩波書店 2,700円
『クロワッサン』961号より
広告