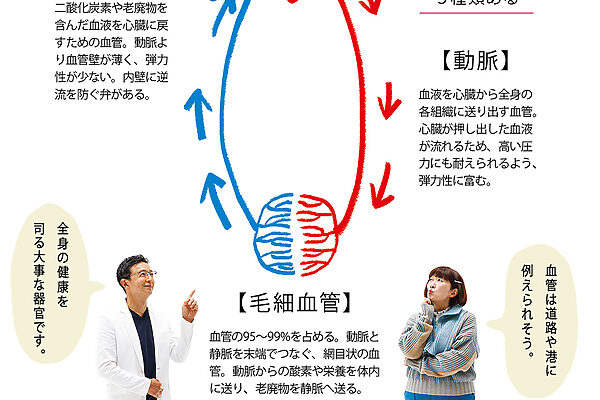作家・佐藤愛子さんインタビュー[前編]
「人は人、我は我ですよ」

物事をビシビシと片づける口舌の良さ、力強く朗らかな笑い声と物差しが入っているかのような背筋は、とても91歳のひとのものとは思われず……
再びのお目もじを願ったところ、小さな笑みを含みつつ、
「あと2、3年もしたら死んじゃうような人間に何を聞くんです?」
ーーそのぶれのない生き方、力強さの源を教わりたいのです!
「ぶれずに生きるとか、佐藤さんのように強くなりたいって言うけれども、それは持ち前におかまいなしの性質であることが前提条件ですから。私のように生きたらとんでもないことになりますよと言いたい(笑)。ぶれずに生きるというのは、いろんなことがあっても平気でいられるかってことですよ」
佐藤さんは1923年の11 月に当時国民的人気を誇る作家・佐藤紅緑(こうろく)と女優・三笠万里子の次女として神戸に生まれる。紅緑に可愛がられて育ち、20歳で結婚するが、戦争から戻った夫はモルヒネ中毒となり、離婚。その後、作家を志し、同志でもあった田畑麦彦と再婚する。田畑は頭脳明晰、哲学的で才能あふれる男だったが、事業に手を出し、莫大な借金を抱える。その借金を回避するため提案された偽装離婚を佐藤さんは呑むが、夫は佐藤さんの知らぬ間に他の女性を籍に入れるわ、その後も気ままに借金に来るわ、家から勝手に金を持ち出すわ。佐藤さんは佐藤さんで、借金取りが面倒だからと、他人の亭主となった男の借金の裏書きをし、三千万円以上を肩代わりすることになる。
「まぁ、あのときの心理は自分でも今、理解できないですよ。当時は面倒くさいばかりで、払やァいいんだろ、払やァ! 金のために大の男が顔色変えるな!っていう(笑)。払える目処なんて全然ないのに」
ーーまだ売れっ子じゃない時期ですよね。
「ぜんぜん。直木賞を取るまではまったく。少女小説を書いてて、原稿料は小遣い程度ですからね」
ーーそもそもどうして物書きになったんでしょう。
「前の結婚で出戻ってきてたわけでしょ。昭和23年頃ね。男でさえも失業者がうようよいる時代ですよ。母は先の先まで考える人だから、このわがまま娘がどうやって生きていくだろうかと心配したんですね。勤めも1週間ともたないだろうし、もいっぺん結婚してもうまくいくはずもない(笑)。兄・ハチローもそうですが、協調性のないのは佐藤家の血統ですから。それで父もいろいろやって最後は小説家になった。小説家っていうのはひとりで書いてりゃいいわけですよ、協調性がなくたって。だからおまえもそれしかない、って母が言ったの」

ーーそれまでにも小説を書いてらした?
「書いてませんね。女学校を出て嫁に行ってたんだから。でも当時、田舎暮らしで姑の悪口を実家への手紙にさんざん書きましてね。それを読んだ父が〝実におもしろい!〟と。つまり泣きの涙じゃなく、姑の人間性っていうものがよく出てると。嫁にやるより物書きになったほうがよかったなあ、とお父さんが言ってたよと、母はそれを思い出したんじゃないかしらね。でも当時は作家で食べていけるなんて人はごくわずかでしたよ。食べていけなくてもいい、下手っぴいでも書いていれば生きるよすがになるんですよ。クリエイティブなことだから。その満足感はあったけど、野たれ死に覚悟でしたね。今の時代に野たれ死になんて考えられないだろうけど、あの時代は戦争に負けてみーんな野たれ死に寸前みたいだった」
ーーでも直木賞を取りました。
「そうですね。借金を背負った段階ではまだ一人前の作家ではなかった。あのときに借金を背負いまくってね、その額に愕然として腹立ち紛れに書いたのが『戦いすんで日が暮れて』。それで賞を取った。友人の川上宗薫(そうくん)が入院していてそのお見舞いに行っていたときに、病室に連絡があって、〝直木賞をお受けいただけますか?〟と。実は迷いましてね。借金取りもたくさん来てますし、賞を取ったらマスコミがどっとやって来る。ふたつが錯綜したら、こりゃたまわらんわ、と思って。宗薫に〝どうしよう?〟って言ったら、ガーゼの寝間着姿のままベッドに腰掛けて、〝しかし、銭は入るぞ〟って(笑)」
借金を原動力に 人間万事塞翁が馬。
「あのとき借金を肩代わりしてなかったら『戦いすんで日が暮れて』という小説は書いてないわけです。そうすると賞も関係ないし、つまりは職業作家になれたかどうかもわからない。だから塞翁が馬とはこのことですよ。我ながら運がいいんだか悪いんだかわからないの! でもおもしろい。いろいろ堪え難いことはあったけど、まあおもしろかったなと思って死ねるというのは、やっぱり幸せだと思いますよ」
『クロワッサン』931号より
●佐藤愛子さん 作家/2016年は『孫と私の小さな歴史』『役に立たない人生相談』、さらに『九十歳。何がめでたい』と怒濤の刊行ラッシュに「いや、ふざけた本ばかりで」と佐藤さん。一族の荒ぶる魂の物語『血脈』、かつての夫への鎮魂歌『晩鐘』は必読です。
広告