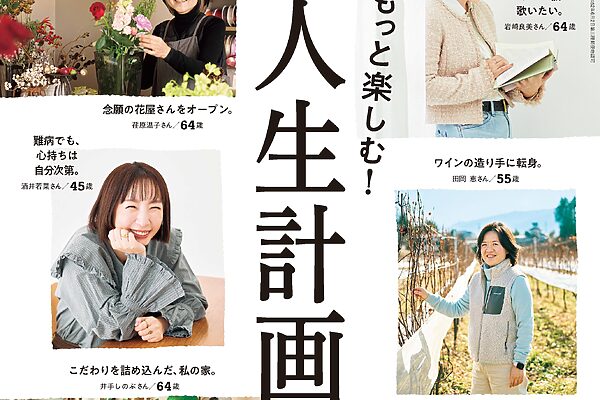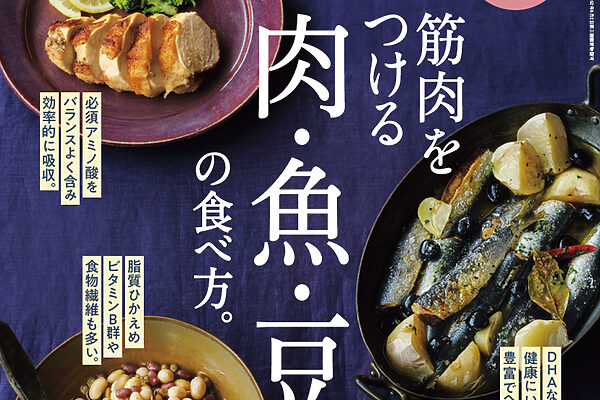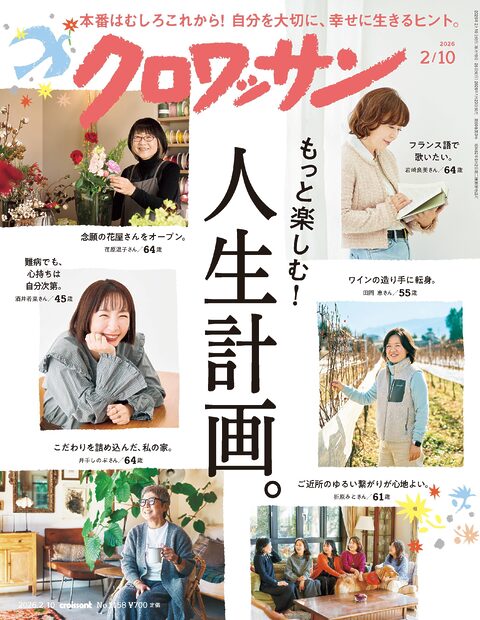考察『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』3話「なんかもう夢ん中にいるみてえだ!」吉原を救うために危うい賭けに出た蔦重(横浜流星)のサンプルプロモーション大成功
文・ぬえ イラスト・南天 編集・アライユキコ
養父・市右衛門、激怒

平賀源内(安田顕)が「序」を書いた『細見嗚呼御江戸』。その奥付にある蔦重(横浜流星)の名前に「これ、入れちゃっていいの?」と唐丸(渡邉斗翔)が訊ねる。こういうところに気付くとは、やはりこの少年は頭がよい。
『嗚呼御江戸』は忘八連合でも極上吉の出来栄えだと大好評。蔦重の名前をその場でも出して功労者だと讃えてくれた鱗形屋孫兵衛(片岡愛之助)だが、はたして蔦重の育ての親である駿河屋市右衛門(高橋克実)は激怒した。
市右衛門「てめえいつから本屋になりやがった!」
殴るわ蹴るわ。こんなに恐ろしい親父さんを止めようとする次郎兵衛(中村蒼)。うすらぼんやりの遊び人若旦那と見ていたが、いいところあるなあ。親父に殴られて鼻血出ちゃったけど、唐丸と一緒に蔦重をかばおうとしてくれて、ありがとう。
しかし市右衛門は養い子が勝手に動いたからって暴力に走るほど怒るのか。養父としてメンツを潰されたという理由だけだろうか。
田沼意次の真意は?
市右衛門の「こんなもんで客が来るわけねえだろ」という言葉は、悔しいが当たっていた。平賀源内の「序」の効果で「細見」は売れたが、客足はいまひとつ伸びす。江戸市中の人々は、「序」を読むだけで満足してしまったのだろうか。手に取って買ってくれれば万歳の歯磨き嗽石膏や「細見」と違い、集客という目的を遂げるにはもう一歩二歩、踏み込んだアプローチが必要のようだ。
その平賀源内当人は、田沼意次(渡辺謙)邸宅にお年賀の挨拶に訪れていた。源内がお年玉ですと差し出したそれを、何も説明されていない内から「『吉原細見』ですか?」と手に取る意知(宮沢氷魚)。おっとり優しいだけのボンボンかと思ったら、意外に世情に通じている?
意次に秩父での銀の採掘状況について訊ねられた源内が、残念ながら銀は出ないが鉄が掘れると答える場面がいい。「伊達家などは鉄の銭で大儲けしたというしな」。仙台藩初代藩主だった独眼竜・伊達政宗を演じた渡辺謙にこれを言わせるのは、大河ならではの遊びですね。
田沼意次には、白河松平家から田安家の次男・賢丸(寺田心)を養子にしたい旨、助力をしてほしいという請願が来ていた。意次は将軍・家治(眞島秀和)に進言する。
意次「あの英明なる若様が、今後なんのお役目にもつけず部屋住みとして朽ち果てるのみとは」
御三卿の田安家、一橋家、清水家は大名家ではない。将軍家に世継ぎがないときに自分たちの家から世継ぎとなる男子を出すために存在する。治める藩を持たないため、将軍にならないかぎりは政治手腕を発揮する機会がないままである。それが残念で哀れである、陸奥白河藩(現在の福島県白河市周辺)の当主になれば、賢丸は持って生まれた才を活かすことができるのではないか……と、こういう理屈だ。この進言は本当に賢丸の才を惜しみ「よかれと思って」のことなのか、それとも白河松平家にせっつかれてうまいこと言っただけなのか。
いずれにせよ、意次のこの行動は老中首座・松平武元(たけちか/石坂浩二)を激怒させた。将軍家、御三卿の継承に関わる事案に意次がスタンドプレーで干渉したことが言語道断だという怒りだろう。
そして、田安家当主・治察(はるあき/入江甚儀)と賢丸の母・宝蓮院(花總まり)も「甘言だ」と怒りに声を震わせる。白河松平家の養子となれば、将軍の座はまわってこない。
賢丸も治察が田安家の後継となる男子を得てからと願い出たが、将軍・家治からの直々の命令は断れなかった。
酷い世界が広がっている
蔦重は大門で、新潟の女郎屋に売られてゆく音羽(大田路)と会ってショックを受ける。彼女は吉原の最下層・河岸見世「二文字屋」の女郎。1話(記事はこちら)で店を訪れた蔦重に「待ちかね山!」と飛びついていたあの子だ。音羽は女衒(ぜげん/売春労働仲介業者)に連れられて旅立った。
「二文字屋」では女郎達が寝込んでいる。唇に潰瘍、手の平から全身にかけて赤い発疹──梅毒の初期症状ではないだろうか。梅毒は主に性交渉により感染する。感染リスクの高い遊女の多くは潜在的な患者であった。梅毒の初期症状で寝込むことを「鳥屋(とや)につく」と呼ぶ。一時的な脱毛症状がみられることから、鳥の羽毛が抜け変わる様子にちなんだ俗語だ。潰瘍、発疹と発熱が治まり、再び客が取れるくらいまで回復すると遊女として一人前と喜ばれたが、治ったわけでなく、この時期は梅毒の潜伏期間に過ぎない。
数年から10年以上経つと全身に腫瘍ができ、筋肉、内臓、骨、脳神経まで侵され死に至る。自然治癒はない。
潜伏期間中の患者から性交渉相手に感染し、その新たな患者がまたほかの人間に感染させ……こうして性病は拡がってゆく。江戸時代の医師・杉田玄白が著作『形影夜話』(文化7年・1810年)で「梅毒ほど世に多くしかも難治にして人の苦悩するものなし」と記し「千人診察するとそのうち七、八百人は梅毒に罹っている」とまで書いた。それほど梅毒は江戸の人々を悩ませていたのだ。
抗生物質・ペニシリンの発見は1928年、梅毒に効くと証明されるのは1943年。蔦重達の時代より150年以上も後である。それまでは水銀軟膏など、薬効が薄く根本治療にならない薬で対応するしかなかった。そして、遊女たちにはそうした治療すら施されるはずもない。
1話で病死した朝顔(愛希れいか)が居た部屋には、咳込む女郎たちが寝かされている。
朝顔と同じく労咳(結核)なのか、それとも風邪なのか。風邪であろうと栄養不足と不衛生な環境で人が死ぬ時代である。
この惨状に、二文字屋女将・きく(かたせ梨乃)が閉業を口にした。
きく「女郎なんて売られてきて、他に生きる術がない」「この子らはわっちが手を離したら終わりだと思ってやってきた。けども……」
親に売られ借金を背負わされたまま、売春以外の道を閉ざされた女たち。女将であるきくが音羽を新潟の女郎屋にやったのは売り飛ばしたというよりも、せめて最低限でも食事できるであろう他の女郎屋で生きてほしいという願いからだろう。
売春を続けさせるのがいいというのかと、現代の感覚では思ってしまいそうだ。しかし、この7年前・明和4年(1767年)に幕府が「間引き禁止令」を出していることを知ると、女将きくの絶望を少し理解しようという気になる。貧しい村では生まれた子を育てられず、間引きが横行した。それを禁止する法令を出さざるを得ないような事態だったのだ。
1話で蔦重が「親兄弟がなくても、白い飯を腹いっぱい食えるのが吉原のはずだ」と嘆いた。このままでは飢え死にしてしまう、ならばせめて女郎屋で生き延びてほしいという親の願いが、女将きくと同じくあったのではないか。遊郭の内側も外側も、酷い世界が広がっている。現代の我々にできるのは過去を知り、今と未来に活かすことではないだろうか。
吉原の不況、河岸見世の現状をなんとかしたいと、蔦重は危うい賭けに出た。
個性豊かな花魁たちがこぞって
「一世一代の頼みがありんす」と花の井(小芝風花)から手紙で呼び出され、引手茶屋で待たされている長谷川平蔵(中村隼人)。そわそわと落ち着かず、髪型チェックに余念がない。今週も可笑しく可愛い。
女郎の絵姿を集めた入銀本(お金を集めて作る書籍)を作る企画がある、出資した額でページの並びが決まるので、自分は誰よりもお金を出して頭(トップページ)を飾りたいのだと平蔵にせがむ花の井。求める額はライバルの出資額30両以上。
その額に、さすがに目を剥く平蔵だが、花の井に手を握られ胸に寄り添われ、さらには禿と振袖新造たちが揃って「拝みんす」「長谷川様」「長谷川様ぁ」
劇団・花の井じゃないか。今週も平蔵がカモにされている!
そして平蔵から巻き上げた50両は、二文字屋に直行。これで当面、二文字屋の女郎の飢え死には避けられた。
その上で蔦重は本の企画を押し進める。大見世の上級女郎たちに営業をかけた。
彼女たちの競争心を煽るため、花の井は50両を出資してトップを飾る予定だと触れ回る。
玉屋・志津山(東野絢香)「どうなんしょう。花の井のような床下手が頭って」
床下手ってアナタ。閨房技術が優れているか否かは枕を共にした相手しかわからないと思うのだが、もしそういう噂を言いふらしている人間がいるとしたら、花の井に振られた男か、あるいは商売敵ではないか。
ともかく、蔦重は次々と声をかけてゆく。
ツンツンしているのは桐菱屋・亀菊(大塚萌香)、上方風のあでやかな結び立兵庫がよく似合う角か那屋・常盤木(椛島光)は「また腹の上で死ぬ男を増やせって?」とすごい自信がおありの花魁、無口なのは四ツ目屋・勝山(平館真生)。企画を聞いて「そりゃ気散じ(憂鬱がまぎれる)なもんだねえ」とのんびり言うのは花魁、扇屋・嬉野(染谷知里)、「いとしき風がふわふわと」と歌が上手なのは角たま屋・玉川(木下晴香)。
個性豊かな花魁たちがこぞって資金を出した。本作成のための元手を確保した上で、蔦重は忘八連合に話を通しに行く。一文も出さなくても営業のための配布本を作れるとあって、忘八はみんな乗り気だったが、駿河屋市右衛門はどうしても許さない。また暴れた末に蔦重に「出ていけ」と勘当を申し渡した。
『光る君へ』製本場面から750年以上
二文字屋の女将きくは、蔦重から受け取った50両を元手に他の見世の河岸女郎たちのための炊き出しを実施している。こっそり受け取ったのだから自分の懐に入れてしまうか、二文字屋の女郎たちのためだけに使ってしまうことだって考えられるのに、ここで生き延びる女たち皆のために……。きくの優しさと心意気を感じる。更に、駿河屋を追い出された蔦重の居場所も提供した。二文字屋で蔦重は、頒布書籍の案を練る。
本屋に並ばないことを逆手に取るのだ。吉原に足を運び、馴染みにならないと手に入らない魅力的な本……まるで、通販や書店委託販売のない頃の同人誌のようだ。同人誌即売会、コミケに直接行かないと、好きな同人作家の作品は入手できなかった。
蔦重は貸本屋を副業としているから、現在人気の絵師は把握済みだ。今回選んだのは北尾重政(橋本淳)! 120人以上の女郎の姿を載せる本と聞いて、
重政「墨摺りで? 一枚絵ならまだしも、本になると似たような絵が延々と続くことになるよ。あんまり面白くねえんじゃねえかな」
書肆(しょし/本屋)の家に生まれ育ち、本のことを熟知している北尾重政なら、このアドバイスが出てくるのは納得なのだ。
カラー印刷ならともかく、黒一色印刷で美人画だけが120人分並んだ本。綺麗だろうけど、確かに面白くはなさそう。
そこで生まれたアイデアが「見立て」。江戸時代には、よく知られた古典作品や故事、歴史上の事件などを当時と照らし合わせて描いた見立絵がジャンルとして確立された。今でいえば「もしも〇〇だったら」などの設定から発想する「現パロ(現代パロディ)」もこの見立絵にあたるだろう。歌舞伎役者を花に見立てた絵も登場していた。
かつて貴族と武家のたしなみだったいけばな(立花)は、江戸時代に入ると経済力ある町人たちの間に普及し、さらにちょっとした場所に飾る「投げ入れ花」が流行した。2話(記事はこちら)で次郎兵衛が花の会に出かける場面があり、生花を入れた桶を担いだ振売が歩く場面もあった。戦乱がおさまった世で花を飾り楽しむ習慣が民衆の間に広がっていたのだ。その花に女郎たちを見立てる発想。
ツンとしてる女郎はわさびの花。夜冴えないのは昼顔。無口なのはクチナシ。文ばかり書くかきつばた──怒られない程度にやりなよ、蔦重。蔦重が女郎たちをそれぞれ思い浮かべて花に見立て、絵師・重政が流麗な筆で次々と描いてゆく。
絵ができあがったら、それをもとに彫師が版木を彫り、摺師が紙に刷る。この場面は江戸時代からの伝統の技を受け継ぐ、本物の職人が演じている。
蔦重「トベラの白玉花魁は枝が大事なんですよ、枝が」
親方「そんなにぃ?」
トベラは花は良い香りなのに、枝を折ると独特の臭いがする。そのことから「トベラの枝」は女性の下半身、ある部分の臭いを指す隠語だ。白玉花魁は蔦重を一発殴っていいと思う。でも「大事」と表現するということは、白玉もそれをアピールポイントにしていて客がつくのかなあ。人の好みは様々だ。
絵ができあがったら製本。しっかり食べて体調が回復した二文字屋の女郎たちが協力してくれた。よかったとは思うが、前述の通り梅毒は彼女たちの体に潜んだままだし、借金を返すために働かねばならない。病み上がりの女郎が客を取っているのがチラッと表現された。笑顔を取り戻したものの彼女たちの不幸は消えておらず、しかしそれでも生きてゆかねばならない。
この場面に、昨年の大河ドラマ『光る君へ』を思い出した。当時貴重な紙を使い、帝の后と貴族の女性たちが『源氏物語』を製本してから750年以上。紙は庶民にとって身近なものになり字を読める民衆が増え、遊女たちが本を作るようになったのだ。日本人は大きな災害や戦乱を経験しながら文化を育んできたのだと、大河ドラマ2作を通じて我々に訴えかけてくる。
出来上がった本を手に、
蔦重「なんか、すーげえ楽しかったなあ」「こんな楽しいこと世の中にあって、俺の人生にあったんだって……なんかもう夢ん中にいるみてえだ!」
いつも笑顔で明るい蔦重だが、今まで一度も楽しい経験をせず、そうした幸せが世の中にあるということを知らず生きてきたのか。彼の、そしてこの吉原で生きている人々のこれまでの人生を思い、泣いてしまった。
できあがった入銀本、その名は『一目千本 華すまい』。
「一目千本」は千本の桜を一目で見渡せるところ、桜の名所・奈良の吉野を指していう古くからの言葉だ。華すまいは花々に例えられる女達の住まい、吉原。そして「はなすまい……放すまい」。吉原の女郎達はあなたの心を捉えて放さないでしょう、という意味にも通じる。
これを出資した遊女と、彼女たちが所属する女郎屋に新しく馴染みになった客に渡してくれと配った。それだけでなく、風呂屋、髪結い床、茶店、居酒屋。江戸市中で男が集まる場所を狙い一冊だけ渡して、これは吉原に来て馴染みになったらもらえる本ですとサンプルプロモーションをかけた。
やるだけのことはやった、あとは九郎助稲荷に手を合わせ神頼みするのみ──。
忘八なら忘八らしく
扇屋宇右衛門(山路和弘)が駿河屋にやってきて、市右衛門に蔦重を許してやれと取り成す。
市右衛門「じゃあ、息子が今日から八百屋もやりますって言ったら許しますか」
宇右衛門「重三だけはよそに出さなかったのは駿河屋を継がせる心づもりかい」
「可愛さ余って憎さ百倍なんてお前さん、まるでヒトみたいなこと言ってるよ。忘八のくせに。忘八なら忘八らしく、ひとつ損得づくで頼むわ。な」
渋い! 抑揚と目の光の変化で、渋くてカッコいいだけではない、怖さも感じさせる。そして粋だ。人間としての八つの徳を忘れなければ務まらないという忘八だが、人間の心も理解せねばましてや大見世の楼主など張れないというわけか。
市右衛門の激怒の理由がここで明かされる。さらりと息子という言葉が出てくる市右衛門と、彼の真意を当てて見せる扇屋宇右衛門。息子……。
宇右衛門が立ち去ったあとに『一目千本』を手に取り開いてみた市右衛門は、たちまち惹きこまれる。ツンツンしてる亀菊はわさびの花。志津山は葛。これに市右衛門が笑いだす。
志津山「他に馴染んだというので髻(もとどり)切られたざんす」
ここで彼女が話しているのは、客の噂話。吉原では馴染みの女郎ができたら、他の女郎に手を出すことを禁ずるしきたりがあった。客をめぐっての諍いが起きるのを防ぐためで、これを犯すと客が髻を切られるなどの制裁をくらう。「花の井は床下手」など、他人の悪い噂話が大好きな志津山は葛(クズ)というシンプルな悪口だろうか。本人にとっちめられたら、白くもっちりとした葛粉のような……などの言い訳が必要そうである。
客を腹上死させる角か那屋・常盤木はトリカブト、無口な四ツ目屋・勝山がクチナシ、「おひさんが」と日光浴していたのんびり花魁、扇屋・嬉野はヒマワリ、ふわふわと……と歌っていた角たま屋・玉川がタンポポ。
いつの間にか隣で『一目千本』を開いていた市右衛門の妻・ふじ(飯島直子)も市右衛門と共に、見立てに笑い転げ「誰よりも、この町を見てんだねえ。あの子は」としみじみ語る。誰よりも吉原を見て、知って、故郷として大切にしている男だ。
そしてついに、吉原に客が押し寄せた。小間物屋も蕎麦屋も大繁盛。馴染みになれば『一目千本』をもらえると聞いて「安い見世なら、俺たちでも」と話している。河岸の切見世の困窮もマシになるだろう。
今回の集客大作戦の立役者の一人である長谷川平蔵は、親の遺産を食いつぶしたからもう来られないと花の井に手紙を寄越した。借金するようなことにならなくてよかったし、あんなにカッコつけていたのに吉原に来られなくなった理由をちゃんと言って寄越すなんて、なんだかんだいって真面目だ。好感度が上がる。
花の井「50両で吉原の河岸救った男なんて、粋の極みじゃないかい」
野暮の極みから粋の極みへ。意中の彼女がこう評していたなんて知ったら、平蔵はどれだけ目を輝かせて喜ぶだろう。岡場所に出入りし、吉原の花魁に恋をしたこの作品の長谷川平蔵なら、小説『鬼平犯科帳』のように、夜鷹を人として扱う鬼平になるだろうなという想像が膨らむ。
しかし、ずっと気になっているんですが。花の井にはうまいこと騙されてくれる平蔵というカモがいたが、この話に乗った120人の女郎たちは出資金をどう工面したのだろう。吉原が不況だから企画が生まれたのである。みんながみんな太い客を持っているわけではないだろうし……見世から無理な借金をしていなければよいが。その辺りは4話以降で出るだろうか。
明るい兆しが見えた吉原とは対照的に『一目千本』を手に暗い情念を滾らせる、鱗形屋孫兵衛。そして、傀儡を操る一橋治済(生田斗真)。
田安治察が22歳という若さで死去、妻子はおらず、弟の賢丸が白河松平家に養子となることが決まった半年後である。陰謀がうごめく気配がする──。
次週予告。蔦重、錦絵に挑む! 本を出すのに一文も出したくないらしい忘八連合。やっぱり資金問題が浮上している。ちょっと待って。なぜか忘八みんな猫を抱っこしてない? 書を以て世を耕し……耕書堂の名が! 展開早いな。田沼意次、田安家から恨まれる。3話は風呂屋の主人としてジェームス小野田がいたが、4話は絵師として鉄拳が登場する!
第4話も楽しみですね。
*******************
NHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』
公式ホームページ
脚本:森下佳子
制作統括:藤並英樹、石村将太
演出:大原拓、深川貴志、小谷高義、新田真三、大嶋慧介
出演:横浜流星、安田顕、小芝風花、高橋克実、渡辺謙 他
プロデューサー:松田恭典、藤原敬久、積田有希
音楽:ジョン・グラム
語り:綾瀬はるか