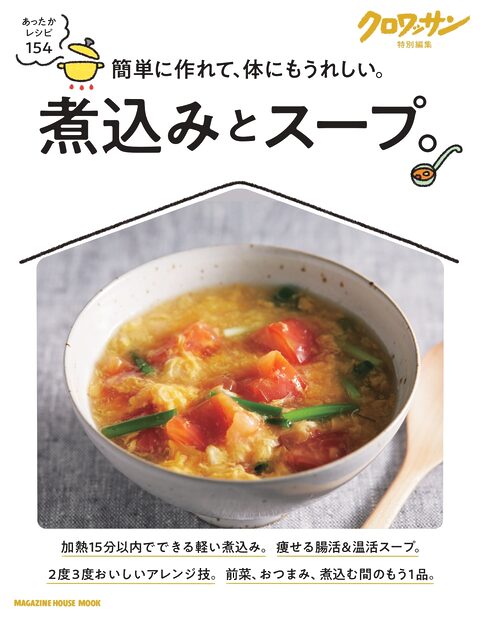考察『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』37話 重すぎる春町(岡山天音)の死…松平定信(井上祐貴)がやばい!蔦重(横浜流星)が錆びた?山東京伝(古川雄大)「蔦重さんのところでは、もう一切書かないっす!」
文・ぬえ イラスト・南天 編集・アライユキコ
期待をかけられる山東京伝

恋川春町(岡山天音)の死。その影響は大きかった。
春町を救えなかった蔦重(横浜流星)と、愛する作家を死に追いやった松平定信(井上祐貴)。後悔に囚われた二人の男が、もがいている。
春町と一緒に黄表紙人気を支えていた作家、朋誠堂喜三二(尾美としのり)は秋田に移った。大田南畝(桐谷健太)も黄表紙から手を引いた。戯作者武士が幕府を恐れて断筆した結果、エンタメ書籍界は作家不足に陥ってしまう。
倹約令による不況も直撃しており、意気消沈の地本問屋仲間の中からは、
「黄表紙は、ここがやめどきってことなんですかね」
諦めの声が上がるが、蔦重は「お武家様が難しいなら町方(町民)の先生にふんばってもらいましょう」と一人奮起する。
だが、蔦重から期待をかけられる山東京伝(古川雄大)は及び腰だ。
同じ町方作家の唐来三和(山口森広)は『天下一面鏡梅鉢(てんかいちめんかがみのうめばち)』絶版処分後、筆を置いて遁走。京伝自身も前年の寛政元年(1789年)、挿絵を担当した黄表紙『黒白水鏡(こくびゃくみずかがみ)』が幕府から御政道風刺と判断され、絶版を申し渡された。作者の石部琴好は江戸所払(えどところばらい/江戸からの追放)を受け、京伝も罰金刑を科せられている。
京伝「俺、目をつけられてるんですよ。もう嫌ですよ、黄表紙」
京伝がこう言うのも無理はない。次は罰金では済まないかもしれないのだ。
「このまま黄表紙の火が消えちまってもいいのか?」と肩を叩く蔦重。
だが書き手として処罰を体験した京伝の顔色は冴えないままだった。
腹を切らせてしまいました
定信は寛政の改革を押し進めてゆく。
老中首座として、棄捐令(きえんれい)を提案する。札差(武家の蔵米を預かり、米商人に売って換金する商人。蔵米を担保とする金融業者でもあった)に武家の借金を帳消しにさせるというものだ。
それでは札差が倒産してしまうと反対する老中・牧野貞長(大鷹明良)を突っぱね、定信は「安心せよ、あやつらが倒れぬ仕組みを考えておいた」と分厚い書類を示した。
定信が示した仕組みについて触れておきたい。棄捐令発布後、実際に札差倒産を防ぐための策として、幕府から札差へ多額の融資がなされた。よって倒産は避けられたものの、武家に貸したら返ってこないというよくない前例ができ、武家への貸し渋りが起こったという。
ドラマ内で顔を見合わせる老中たちは、こうした貸し渋りを予想して危惧しているのだが、定信は自分の路線を譲らない。
さらに、中洲新地(現在の東京都中央区日本橋中州付近にあった当時の歓楽街)を取り壊す案を打ち出した。田沼意次(渡辺謙)の政策で開発され、発展した街だ。
この取り壊しは実際のところ、風紀取締り以外に隅田川の洪水対策目的もあったのだが、ドラマでは田沼時代の悪しき象徴、俗悪の巣窟だと敵視する定信の姿勢が際立つ。
老中たちが「無理筋では」と言い出せない空気の中、一人気炎を吐く定信。
「借金さえなくせば、本来の正しき心で政ができるということだ!」
「遊ぶところがあるから人は無駄金を使うのだ。遊ぶところを無くしてしまえばよい!」
孤立してゆく気配にも構わず、声を上げ続ける。
もっと、もっと世の中を正しく。正しい政をせねばならぬ。
その言葉は、勢いとは裏腹に悲鳴に似た響きを帯びてゆくのだった。
本多忠籌(ただかず/矢島健一)は「世の中は思い通りには動かぬものです」という自分の諫言(36話/記事はこちら)は届かなかったのかと無念そうに目を伏せる。
爆走する定信を諫める人物が、もう一人いた。
徳川御三家・紀伊藩主、徳川治貞(高橋英樹)だ。見舞いに訪れた定信に、国学者・本居宣長(もとおりのりなが)からの意見という形を取って諭す。
「そなたが間違っているとは言わぬが、物事を急に変えるのは良くないと言うておった」「『悪を無くせるとは思わぬほうが良い』とも」「(善悪を)己の物差しだけで測るのは危ういと言うことだ」
病を押して、若き老中首座を導こうとする穏やかな言葉だ。その温かさに定信は身を震わせ、本心を打ち明ける。
「『世は思うがままには動かぬもの』。そう諫言した者を私は腹を切らせてしまいました。その者の死に報いるためにも私は、我が信ずるところを成しえねばなりませぬ!」
……えっ。そういう方向の結論ですか? 春町先生も極楽で驚いているだろう。
真面目な若者が自分で自分を追い詰めてゆく姿に、哀れを覚える。
てい、眼鏡をスチャッと外す
定信の命令によって歓楽街・中洲が取り壊され、江戸市中の岡場所(幕府非公認の私娼屋が集まった地)の取り締まりも強化された。
かねてよりの法令通り、私娼は吉原に送られる。切見世(吉原の最下層の遊女屋)が並ぶ羅生門河岸、浄念河岸は客を引く女たちで溢れかえった。
その様子を目にした蔦重は眉をひそめる。
蔦重「もう見世にもなっちゃいないようですけど」
りつ(安達祐実)「とても抱えきれる人数じゃないからね」
蔦重の目の前で女郎が「わっちは一切(一回)24文だよ」「あたいはもっと安くするよ」と男に声をかけ「倹約のご時世だぞ。うぬらも倹約しろ」と値切られている。
かつて、切見世・二文字屋の女将、きく(かたせ梨乃)は「身を売るよりほかに術がない女たちを、わっちが手を離したら終わりだと思ってやってきた」と語っていた(3話/記事はこちら)。
最低限食べさせてやらねば、守ってやらねばと考えるような楼主不在では、女郎たちはどうなることか。
倹約令と棄捐令の影響で吉原にも不況が押し寄せているのを目の当たりにし、いよいよ倹約を吹き飛ばす作品を世に出さねば、社会の流れを変えねばと意気込む蔦重。
京伝と喜多川歌麿(染谷将太)を呼び出し、吉原を救う作品を出したいと依頼する。
歌麿には、絢爛豪華な女郎を絢爛豪華に描いてほしいと、京伝には、倹約の結果皆が貧乏になり、そのツケは立場の弱い者に回されるということを面白おかしく伝える黄表紙をと頼んだ。
そこへ割って入る蔦重の妻・てい(橋本愛)。
てい「お二方とも。どうか書かないでくださいませ!」
蔦重の指示通りの本を出せば、歌麿も京伝も、耕書堂も無事では済まない。幕府からお咎めを受けるだろう、書かないでほしいと伏し、意を決して蔦重に向き直り、諫める。
てい「旦那様はしょせん、市井のいち本屋に過ぎません」「立場の弱い方を救いたい、世をよくしたい。そのお志はわかりますが。少々己を高く見積もりすぎではないでしょうか!」
と、眼鏡をスチャッと外す。これは、一歩も退かぬというていの心の表れ。
「書を以て世を耕す大望を抱くからこそ、わずかな間の恥や苦労は耐え忍ぶべき」だと「韓信の股くぐり」の故事を出して説く。
その上で、春町が書いた『金々先生栄花夢』以前の黄表紙──青本に戻ることを提案した。青本はもともと昔話や教訓を説いた本だったのだ。かつて、花魁・瀬川(小芝風花)や次郎兵衛(中村蒼)が「青本はつまらない」と手に取らなかったことが思い出される。
この路線なら、お咎めを受ける危険はないはずというわけだ。
京伝は温故知新だと乗りかけたが、蔦重は激怒した。
春町先生は自害したのに、自分たちは保身に走るのか。『金々先生』以前に戻るということは、恋川春町の功績、生きていた証を消すことだと憤りをあらわにする。
だが、ていは引き下がらない。『鸚鵡返文武二道(おうむがえしぶんぶのふたみち)』出版には、危険だとわかっていながら止められなかった後悔がある。耕書堂の女将として、これ以上犠牲者を出すわけにはいかないのだ。
てい「春町先生のご自害は、私たちに累を及ぼさないためでもありました」「ゆえにお咎め覚悟で突き進むことは(春町先生は)望んでおられぬと存じます!」
直球の正論だが、蔦重の心には届かない。
その様子をいたたまれぬ思いで見る京伝と歌麿。
『傾城買四十八手』誕生
歌麿邸で語らう京伝と歌麿。
歌麿「常の蔦重なら、もっとしたたかに『そうきたか』ってことを考えるよな」
京伝「春町先生への思いに囚われ過ぎてんのかねえ」「荷、背負いこみ過ぎじゃねえ?」
身動きできなくなった人間のことは、傍から見ている者のほうがよく理解できるもの。
この場面で、茶を運んできた歌麿の妻・きよ(藤間爽子)の、チラリとアップになった足首を見て、呻き声が出た。
ドラマ前半の場面で気にはなっていたのだ。きよの足首に赤い腫瘤があることを。いや、そんなまさかと打ち消したのだが、この場面ではその腫瘤が増えている。
嘘でしょ、やめてよ……歌麿とおきよさん、こんなに幸せそうなのに。やっと穏やかな生活を手に入れたのに。身を売るしか術のない人々の間に蔓延した病が、きよの体を蝕んでいるのか……絶望。
歌麿と京伝は、きよのこれまでの辛い境遇に思いをめぐらせ、蔦重から注文された作品について話し合った。
倹約の世では社会的弱者が買い叩かれる。そうした弱い者にツケが回るというのは、蔦重の言う通りなのだ。「どうしたもんかねえ……」と思案する京伝、歌麿が襖に描いた写実的な花、ありのままの姿の草花に閃いた。
洒落本の傑作・山東京伝『傾城買四十八手(けいせいかいしじゅうはって)』の誕生である。
吉原のさまざまな見世の女郎と客の会話と駆け引きを描いたもの。写実的な描写と人物の内面まで見え隠れさせる自在な筆致が、読む者をしてそこに居合わせるかのような感覚に誘う。
若い頃から吉原で遊び尽くして、女郎と客たちのありのままの姿を多く見てきた通人、山東京伝ならではの作品といえるだろう。
京伝が耕書堂に持ち込んだ原稿を、ふぅん……という顔で読んでいた蔦重は、通りかかった手代・みの吉(中川翼)に感想を求めた。
試し読みということを忘れて夢中で読みふけるみの吉。
みの吉「自分がこの場にいるような気になって」「最初の話の女郎が、妹に似てまして。幸せになってほしいって」
その感想を聞いた蔦重は居住まいを正し、
蔦重「女郎を姉妹や知り合いのように思わせる。幸せになってほしいと願わせる。これ以上の指南書はございません。うちで買い取らせてください」
と、京伝に頭を下げた。
架空の人物であっても、作中の女郎に心があり、生きてきた背景をまざまざと感じられれば、幸せを願わずにはいられない。きよの幸福を願うのと同じだ。
この本を読んだ者は、実際に足を運んで女郎と向き合ったとき、ぞんざいに扱う気にはなるまい。いい客を増やすことは吉原を救う一手になりえる。
京伝は耕書堂に作品を提供したのだった。
この洒落本なら幕府に目をつけられることもないだろう。京伝が蔦重の依頼に応えて一件落着。と思ったら、悶着が持ち上がる。
蔦重の怒り
寛政2年(1790年)正月。山東京伝の新刊『心学早染草(しんがくはやぞめぐさ)』が地本問屋・大和田安兵衛の店から出版された。
主人公の男の良心である善魂(善玉)と誘惑の道に引き込もうとする悪魂(悪玉)がユーモラスに描かれた山東京伝の代表作、これまた傑作である。
「これ知ってますか?」
鶴屋喜右衛門(風間俊介)から手渡され、パラパラとめくった蔦重の機嫌がみるみる悪くなる。
短気は損気ですよという風に止める鶴屋の声も聞かず、座布団蹴立てて京伝のもとに走った。
京伝は正月の昼間から、吉原・扇屋宇右衛門(山路和弘)の見世の座敷持花魁・菊園(望海風斗)の座敷に居た。おりしも「菊園を身請けしてやっちゃくんねえか」と扇屋から持ち掛けられている真っ最中。
扇屋「馴染んで、もう?」
菊園「3年。月の半分はここに戻られんす」
扇屋「そりゃもう女房じゃねえか」
菊園「毎月のお小遣いも」
扇屋「もうおっかさんじゃねえか!」
この場面の会話のテンポ、落語のようで笑ってしまう。そうかぁ京伝、女郎買いに来てるというよりも花魁からお小遣いまで貰ってるのかあ。そりゃそろそろ責任取れと言われるわ。
下帯一丁の姿で扇屋に膝詰めで詰められて、きまり悪そうな京伝。
そこに蔦重が怒鳴り込んできた!
蔦重の怒りの矛先は、よその版元(板元)で書いたことではなかった。
『心学早染草』は定信の掲げる「倹約・正直・勤勉」政策に乗って流行した学問、心学を面白おかしく伝える黄表紙だったのだ。
蔦重「こんなに面白くしちゃ皆真似して、ふんどし担いじまうじゃねえかよ!」
ふんどし──越中守・松平定信の政策を持ち上げる黄表紙が流行ったらどうするんだ、春町先生に草葉の陰から怒られるぞと責める。
その勢いに怯えながらも、京伝は反論する。
京伝「面白えことこそ黄表紙にはイッチ大事なんじゃねえですかね? ふんどしを担ぐとか担がないとかよりも。面白くなけりゃ、どのみち黄表紙は先細りになっちまうよ」
現政権への反逆的作品でなければ、意味はないのか。読者が喜ぶ面白い作品を世に出すことこそが、クリエイターの存在意義ではないのか。この反論に、蔦重の怒りは頂点に達した。
蔦重「何度言やぁわかんだよ! 戯け者はふんどしに抗っていかねえと、一つも戯けられねえ世になっちまうんだよ!」
音を立てて、黄表紙が京伝の頭に振り下ろされる。
な、殴った! 蔦重が……本屋が本で、作家の頭を。なんということだ。
ここに至るまで、じわじわと進む蔦重の感覚の錆びつきが気にはなっていた。
耕書堂が吉原にあった頃から弟のように接してきた京伝が相手のせいか、春町や喜三二ら武家作家に対する時のような丁重さがない。
「俺、先生の書いたものが読みてえです!」の、おなじみの殺し文句が出てこない。
ただ、作家への執筆依頼は蔦重だけでは成功しなかったことのほうが多い。振り返ればいつも、歌麿、喜三二、春町……皆が助けてくれていた。周りの協力が得られない蔦重は、こんなにも弱いのだ。
弱いから、思い通りにならないと苛立つ。「ああ?」という威嚇も、怒ると手が出る姿も、駿河屋市右衛門(高橋克実)そっくりだ。こんなところ、義理の父に似ないでよい。
蔦重の醜態は春町の死による心の傷のせいか、不況が余裕を奪ったせいか。それとも、これが老いなのだろうか。蔦重はこの寛政2年で40歳。
殴られた京伝がきっぱりと言い切った。
「蔦重さんのところでは、もう一切書かないっす!」
売れっ子の山東京伝だ。殴られてまで耕書堂で書くこたぁないわな……。
ふうん? ああそう、という顔の蔦重だけど、作家がいなければ困るのはあなたでしょ。
どうすんの。
次回予告。……と、その前に、今後の展開のために触れておかねばならない場面がある。
「尊号事件」と治済、定信の対立
一橋治済(生田斗真)が定信に「いかがとなっておる?」「あれは認めてもよいと思うがのう」と示唆していた「朝廷よりの例の件」とはなんだったのか。
ことは、朝廷から幕府に119代・光格天皇の父、閑院宮典仁親王に「太上天皇」の尊号を贈りたいという打診に始まる。
光格天皇は118代・御桃園天皇の養子である。実父の閑院宮典仁親王は113代・東山天皇の皇孫だ。息子が父よりも位が上であるのはいかがなものかということで、譲位した天皇の尊号「太上天皇」を贈りたいとなったのだ。
江戸時代、朝廷の公的な決定には幕府の許可が必要である。この件について通達を受けた定信は、皇位についたことのない人間が「太上天皇」となるのは先例がないとして反対した。対して朝廷側は、鎌倉時代の後高倉院、室町時代の後崇光院の先例を出して反論。
この論争に関わった公家が、幕府側から処分を言い渡されるなど、大きな騒動となった。
結局、朝廷側は尊号を諦め、幕府側は閑院宮典仁親王に1000石加増して帝の父としての面目が立つように計らい、幕引きとなったのである。この顛末を「尊号一件(そんごういっけん)」或いは「尊号事件」と呼ぶ。
息子が父よりも上の位に──そうした父子がこの江戸城にもいる。治済と11代将軍・家斉(城桧吏)だ。治済は、定信に太上天皇の尊号は認めてもよいのではないかとそれとなく言い渡していたのだ。しかし、結果は先述の通り。
治済「太上天皇の奏上は、不承知と返答したそうじゃの」
さりげなく確認してはいるものの、腹に一物抱えているらしき治済。この「尊号事件」は定信の進退にも大きく関わってくるのだ。
定信は虎の尾を踏んでいることに気づいているのか、いないのか。
田沼意次に負けぬ専横ぶりだと皮肉る治済に、
定信「上様の命とあらば、いつでもお役を辞する覚悟にございます!」
山積みの懸案、自分以外に為しえる者がいるならばと啖呵を切った。
おいおい、おーい。このドラマ一番のクセモノ・治済を相手に、そこまで言い切って大丈夫なのか。
あらためて、今度こそ次回予告。「黄表紙、浮世絵、そんなものは出さねばよいのだ」。定信ぅ、黄表紙ファンだった君がそんなことを言うのかぁ。おお! 西村屋さん(西村まさ彦)、鱗形屋さん(片岡愛之助)再登場! お久しぶりです! 待て待て待て。おきよさん噓でしょやめてよ、早すぎる。
蔦重「申し訳ございませんでした」。誰に謝ってるの、京伝先生? どっちにしろ謝ったほうがいいよ。
38話が楽しみですね。
*******************
NHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』
公式ホームページ
脚本:森下佳子
制作統括:藤並英樹、石村将太
演出:大原拓、深川貴志、小谷高義、新田真三、大嶋慧介
出演:横浜流星、生田斗真、染谷将太、橋本愛、古川雄大、井上祐貴 他
プロデューサー:松田恭典、藤原敬久、積田有希
音楽:ジョン・グラム
語り:綾瀬はるか
*このレビューは、ドラマの設定をもとに記述しています。
*******************