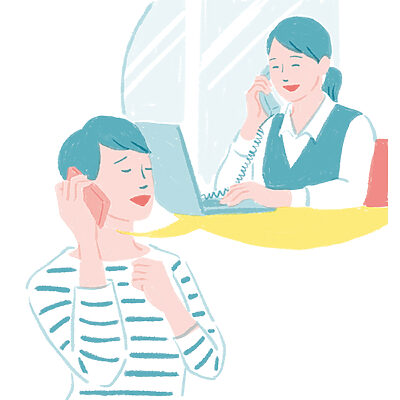『幸あれ、知らんけど』平民金子 著──「ま、えっか」としながらも言葉を紡ぎ生きていく
文・嶋田詔太

ときおり本の著者からサイン色紙をいただくことがある。一種の販促物でもあり、普通は「〇〇書店さんへ」という宛名と著者のサインに、「いつもありがとうございます」のような一言が添えられているものだけれど、この度、平民金子(へいみんかねこ)さんから届いた色紙は、漫画の『魁!!男塾』で描かれる昭和の倫理観がいかに滅茶苦茶かについてが全体の2/3。そして、最近では普通の人はまず文芸誌など読まないことを嘆く挨拶へと続き、その後に自身の新刊の案内がはじまろうとするところでスペースが足りなくなり、唐突に話が打ち切られる。
何とも平民金子さんらしく、そもそも文芸誌(『文學界』)で連載していた「めしとまち」も、日常のエッセイという建前ながら、時に、周囲の傍若無人な振る舞いを耐えかねた平民金子さんが、M60機関銃で自分の頭を撃ちぬき作者死亡で終わったり、またトークイベントを開催すれば、その時間が10時間だったりと、とにかく予定調和を嫌う、「サーチ・アンド・デストロイ」を叫ぶイギー・ポップのパンク精神、アナーキスト大杉栄の「美はただ乱調にある」を地でいくような人物。
そう聞くと、よほど当人は破天荒で無頼な生活を送っているのかと思われるかもしれないが、コロナ禍の2021年から2024年にかけての新聞連載のエッセイに、新たに書き下ろされた文章と日記からなる本書で綴られるのは、神戸の下町での、妻と小学生の娘とのささやかな日常であり、成長していくにつれて、いつかは忘れてしまうかもしれない、路上で死んだアゲハ蝶を拾った日のこと。通学路を並んでヒカキン&セイキンのYouTubeのテーマソングを歌いながら歩いた日のこと。炎天下の歩道橋で物乞いのおじさんを見かけた日、5枚の百円玉をおじさんのお椀に入れた後で、娘に話しかけたこと。
時の移ろいと共に、街も変わっていく。親子で何度も通った市立の水族園は高級リゾート会社が運営するレジャー施設になり、平日は閑散としていた動物園の小さな遊園地も存続は厳しい。ひなびた、ゆえに日常の延長線上で気楽に過ごせた場所は、お金を使って非日常を楽しむ場所にとって代わられていく。
「あほんだら、なにしてくれとんねん」という行き場のない想いが、むしろ、こちらの方がサーチ・アンド・デストロイで進む社会の中でこだまする。それでも日々は続く。3年後、須磨海浜水族園の跡地に出来た須磨シーワールドへ、小学3年生になった娘と出掛ければ、
「くやしいけど、来たら来たでおもろいな」
「あほんだら、なにしてくれとんねん」と思うし、「ま、えっか、しゃあない」とも思う。
今はもう、どう思えばいいのかわからない。わからないまま平民金子さんは言葉をつむぐ。いつか忘れるかもしれないし、思いだすかもしれない今日の出来事、かわした会話、街の景色を。そして祈る。幸あれ、と。
「祈りは、ただそうするほかない片思いのような感情なのだ。」
『クロワッサン』1145号より
広告