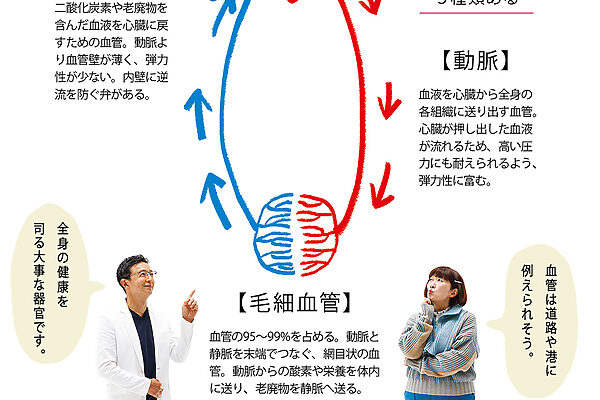『僕らだって扉くらい開けられる』著者、行成 薫さんインタビュー「人間の存在価値を描けたらと思っています。」

撮影・山口真由子
超能力者を描いた小説。子どもだまし?と敬遠するなかれ。各章には超能力の説明があり(これも重要な仕掛けのひとつ)、登場するのは、念動力(テレキネシス)はあれど右に10㎝しか動かすことができない会社員、残留思念を読み取れる(サイコメトリー)のにトラウマと極端な潔癖性ゆえ対象物に触れない女子高生、一日に1度金縛り(パラライズ)が可能だがその度に毛髪が抜けてしまう正義漢。超能力のはずがその効力も所持者もどこかショボくて情けない。
著者・行成薫さん曰く、「できるだけ持っても意味がなさそうな人にそれぞれの超能力を割り当てました」。結果、その力に振り回され、奮闘する市井の人人の様は笑えつつ共感でき、どこかほっこり。すべての超能力者たちが結集する最終章は、各章で張られた伏線が回収され、その爽快感と温かさに涙してしまうほど。
さぞや入念に練られたプロットを立てたのかと思いきや、
「僕はプロットを立てるということをあまりせず、編集者さんと雑談しながら固まっていくタイプなんです。オチも〝だいたいこんな感じ〟ぐらいで書き始めていくので、当初の想定とは全然違ったものに。ラストに向けて自分でもわからないまま随所に蒔いた種が、最後にすべてうまくはまってよかったなぁと(笑)」
ネタ帳を作ることもない。あるのは「書きたい一場面」、あくまで頭の中に浮かぶ映像から生まれてくるとか。目指すのは世代性別を問わないエンターテインメント作品だが、一貫したテーマとして据えていることはある。
「根底に死生観があって、そこから派生するテーマが大半です。今回もどういうふうに生きるか、人間の存在価値を書いたつもりです」
超能力者たちは自分たちのふがいなさに迷い、時に立ち止まるが、まったく能力を持たない〝一般人〟北島というキャラクターには、特に著者の優しさが感じられる。
「会社の中では後輩から見ても役に立たなくて、性格にも難がある困った先輩なんだけど、ちょっと視点を変えて見たら、ある人にとっては“いいお兄ちゃん”で。そうやって見る角度を切り替えることで価値が変わる人もいる。世界にしても、今、自分が何したって変わらない、自分の存在は無意味と卑下している人は多いですよね。確かに目に見えて変わることはあまりないけど、廻り廻って変化することはいっぱいあるはず。だからもうちょっと自分で個々の価値を見出していったほうがいいんじゃないかなと思うんです」

集英社 1,600円
『クロワッサン』970号より
広告