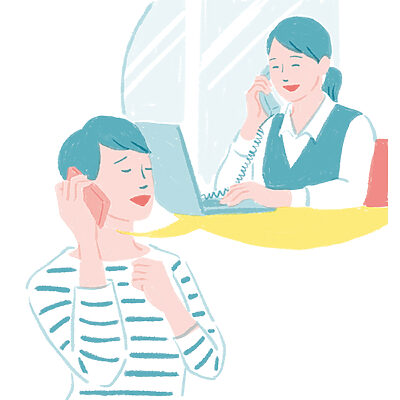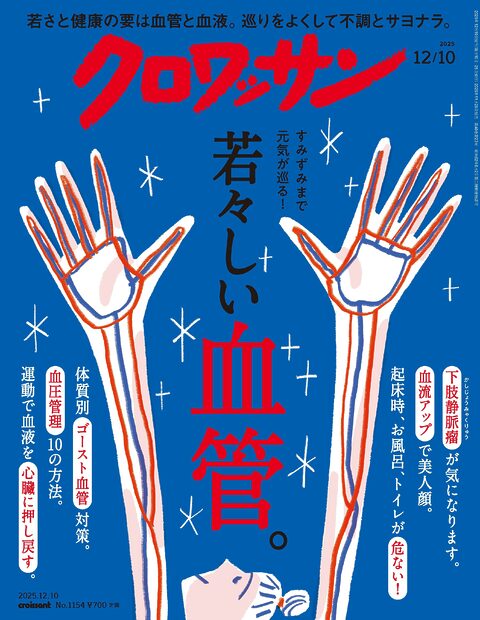【後編】94歳、辰巳芳子さんからの伝言。生ハム作りを通して学んだ、生きること、考えること。
撮影・青木和義、小林庸浩 文・越川典子
「生ハムを継いでもらいたい、伝えたい。本能的にそう思う。」

「生ハムは『作る』という言葉では表せない、発酵、熟成という時間の経過が必要な『仕込みもの』。それ自体の味わいもですが、発酵調味料としても使えるんです」と辰巳さん。
「ヨーロッパでは発酵調味料を持っていないでしょう。ですから、生ハムの切れ端をちょっと入れて、料理の底味を上げるんです。刻んでトマトソースに入れれば奥行きのある味になる。サイの目に切って、ゆっくり炒めて脂分を出して、その脂を使うなんて芸当もできる。ステーキの仕上げや魚のソースに加えれば味にぐっと深みが出る。カラカラに炒めたものは、赤ぶどう酒と食べたり、ピッツァにパラパラとふったり。骨はスープを引き、余すところなく使っていく」
定期的に試食会も開かれている。今回は、東京・恵比寿にあるフレンチレストラン『モナリザ』が会場だ。総料理長・河野透さんは、25年前に初めて辰巳さんの生ハムを口にしたときの衝撃を覚えているという。
「ほかでは味わったことのない味。クセやにおいはないのに、旨み、風味がぎゅっと凝縮されている、まさに熟成の味わい。いつでもいくらでも食べられる。最高峰の生ハムと言えます」
集まったのは、茨城の栗豚を提供し、生ハムの栄養について研究する東京大学大学院農学生命科学研究科准教授の李俊佑さん、早稲田大学理工学術院教授の中尾洋一さん、仕込みから参加している『グランド エル・サン』料理長の片倉忠直さんだ。片倉さんは、山形・庄内で生ハム作りを計画中でもある。
「仕込みもの」が、人を育ててくれるんです。
助手たちも、この3年間、辰巳流をゆるがせにせず、正確に再現。技術を体得しつつあるが、同時に「技術はきちんと『仕事』として成り立たせなければ伝承されない」(辰巳さん)、のも事実。プロジェクトが稼働した理由はそこにある。早大の中尾さんは、
「調べたところ、辰巳さんの生ハムの脂肪は2カ所に融点が認められることがわかりました。熟成の過程で脂肪の組成がどのように変化するのか。栄養効果はどうか。ヨーロッパの生ハムと日本の生ハムとは熟成に関わる微生物が違うはずですから、面白い調査になると思っています」
「熟成の力が科学的に解析されるのはすばらしいわね」と辰巳さん。
「この分析的な視点は、食べる人、料理をする人にも必要なの。生ハムは、究極の保存食で、スペインでは何ごとかあれば、生ハムを1本かついで逃げたというでしょう? 肉を干して食べる意味に気づかなければ」
スペインの生ハムと日本のかつお節は同次元。
そのヒントを、日本のかつお節に求めているのが辰巳さんだ。
「たんぱく質を発酵、熟成させたものということで、かつお節と生ハムは同質。いや、そうね。同質というより、『同次元』と考えてよいと思う」
保存がきくだけではない。人間が欠かさず摂取しなければ生きられないたんぱく質を、体内に極めて吸収されやすくしているのだ。
「間違いのないように仕込みさえすれば、あとは時間が仕上げてくれる、保存食、仕込みものは、すばらしいです。だからこそ、誰でも仕込み仕事をしてほしい。たくあんでも梅干しでも、仕込みのよさは、その過程が人間を育てることです。一度、手のかかることをすれば、あとはついてくる。人生も一緒だ。するべきことを難なくする人になるということは大事です。私自身も、仕込みもので育てられましたから」
研鑽の末に手に入れた生ハム、
「有事のときは、私も1本かついで逃げようと思ってる。しばらく生きながらえるでしょ(笑)」
「スペインの高名な料理人が見せてくれた、 これが生ハムの食べ方の王道です。」


辰巳芳子(たつみ・よしこ)さん●「良い食材を伝える会」会長、「大豆100粒運動を支える会」会長。料理家であり、随筆家としても名高い。独自のスープ料理をまとめた『あなたのために』はロングセラー。『野菜に習う』『さ、召し上がれ。』(共に小社刊)など著書多数。
『クロワッサン』1003号より
広告