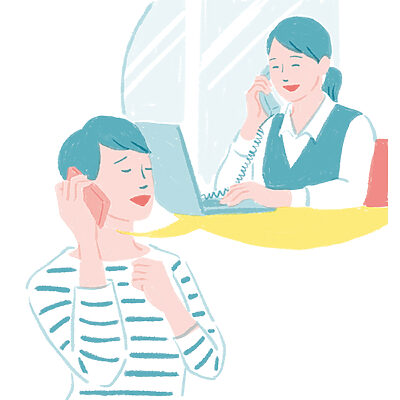民藝の心をつないで300年。一子相伝、小鹿田焼の里を訪ねて
撮影・竹内さくら 文・輪湖雅江

大分の「皿山」で出合う、変わらぬ風景と伝統の手仕事
「日田の皿山(さらやま)ほど、無疵(むきず)で昔の面影を止めているところはないでありましょう」。著書『手仕事の日本』にこう綴ったのは民藝運動の創始者・柳宗悦。九州北部では焼きものの里を皿山と呼ぶ。
福岡空港から車で約1時間半。大分県日田市の山間部で作られているのは、日本の民陶を代表する小鹿田焼。柳が目にした風景をそのまま封じ込めたような集落では、川に沿って9軒の窯元が点在し、水流を利用して土を搗く唐臼のギギー、ゴットンという音が、あちこちから時間差で聞こえてくる。
「地元の山で採取した土を唐臼で細かく砕き、成形には足で蹴って回す“蹴ろくろ”を使います。釉薬は藁灰や木灰などを用いて自作し、焼成は薪を使う登り窯。機械の力に頼らず、すべて人の手で作られているんですよ」
集落の高台にある「小鹿田焼陶芸館」の牛王(ごおう)賢治さんがそう話す。いわく、小鹿田焼が始まったのは江戸中期の1705年(1716年説も)。
「16世紀末、豊臣秀吉とともに朝鮮へ出兵した筑前藩主が陶工を連れ帰り、福岡県直方(のおがた)に窯を開かせます。彼の孫が創設したのが小石原(こいしわら)焼。18世紀になり、その陶工を日田に招いて始まったのが小鹿田焼です。当初から窯は家族単位。息子1人が窯を継ぎ、弟子はとらない一子相伝を守り続けています」
そんな小鹿田焼が世に知られるようになったきっかけは、1931年、柳宗悦がこの皿山を訪れたことだった。
小鹿田焼の原点は、米や水を貯蔵する甕や壺作り。その技術をもとに、皿や碗など日常の器が焼かれ始めたのは100年ほど前のことだ。柳が福岡の久留米で偶然出合った器に見出したのは、生活道具としての美しさだった。
「どうしても今出来のものとは思えない。それほど手法が古く形がよく色が美しい。あるものは遠く唐宋の窯をさえ想起させた」(著書『日田の皿山』)と讃えた柳は、世間にはほとんど知られていなかった小鹿田の情報を一生懸命に探し出し、自ら足を運ぶ。さらに1954年には、民藝運動を牽引した陶芸家の一人であるバーナード・リーチも皿山を初訪問。約3週間滞在し、陶工たちにピッチャーの取っ手作りを指導した。以来、平べったい取っ手がついた美しいピッチャーは、小鹿田焼のシグネチャーの一つとなっている。
使いやすい形こそが美しい。未来を見据える〈坂本工窯〉へ
「小鹿田が器作りだけで食べていけるようになったのは、民藝運動以降の話。それまでは、山や田畑の仕事の合間に作陶をする“半農半陶”でした。僕の頭の片隅には、当時の人が伝統を途切れさせることなく繋いでくれたことへの感謝がいつもある。それをどう次世代に継いでいくかが課題です」
そう話すのは、集落の中ほどに立つ〈坂本工窯〉当主の坂本工さん。リーチの来訪時に世話役を務めた故・坂本茂木(しげき)さんの息子で、現在は長男の創(そう)さんと2人で窯を守っている。
「小鹿田は土地が狭く、陶土にも限りがあります。これ以上、人も窯も増やせなかったことが、一子相伝の形をとった理由かもしれませんね。窯元も多い時は14軒ありましたが、今は9軒。後継者がいなくて廃業した窯もあるし、僕自身は正直、継がなくてはいけない重圧から逃げ出したい気持ちもありました。それでも頑張れたのは、柳宗悦が小鹿田に残してくれた“みだりに昔を変えるな”という言葉のおかげです」
そんな坂本さん父子の器を手に取ると、まず軽やかな印象にびっくりする。
「民陶ですから効率的に数をたくさん作るのが基本。50種類以上ある器を、それぞれ1万点2万点と作り続けていれば、技術や小鹿田らしさは身に付きます。そのうえで、僕は薄くてきれいな形に惹かれている。きれいな形とは手に取りたくなる形です」
一方、仕事を始めた年から個展を開き、話題を集めていたのが35歳になる創さん。その器が全国の器店でひっぱりだこなのは、勢いのよさと繊細さが同居する意匠の美しさを、生活道具として優れた形が支えているからだろう。創さんの器も薄手で軽く、7寸8寸の皿でも片手でラクに扱える。何より、器をつかんだ時の感触が気持ちいい。
「一般の大皿は縁が薄くて高台周りが厚い。でも僕の器は反対。縁に近いほうに重心があると持ちやすいし、軽く感じるから使いたくなる。理想は、食器棚の一番手前が定位置になる器。割れちゃってもまた欲しくなる器です」
ちなみに、個展を開くのは「もちろん小鹿田では常識破り」なのだそう。
「でも、僕があと40年作陶できるとして、今の市場だけで小鹿田焼を繋いでいけるのかというと不安しかない。民藝好き以外の人にも使ってもらいたいし、海外も視野に入れています」
坂本工窯
小鹿田焼開窯当時から続く三家(柳瀬家、黒木家、坂本家)の一つ。現当主の坂本工さんは、小鹿田焼協同組合の理事長も務める。確かな技術に支えられた美しい造形やのびやかな意匠が特徴。工房の軒先では器の販売も行っている。
●大分県日田市源栄町176
〈小袋窯〉で22歳の若手陶工とグラフィカルな器に出合う
すっきりと片づいた工房の棚に、細かな文様が規則正しく刻まれた「飛び鉋」の鉢や皿が並んでいる。飛び鉋の雰囲気は窯元によってさまざまで、〈小袋窯〉の場合は、「線が短く細く、間隔は狭いけど、やわい(きつくない)」と当主の小袋道明さん。工房の凛とした佇まいとも、どこか似ている。
「きっちりしてるのが落ち着くんです。道具がいつもの場所にあれば、欲しい時にすぐ手に取れる。ろくろでも削りでも、小さな工程を正確に行うかどうかで、仕上がりが違ってきます。器は、陶工の手元だけで作られるのではなく、制作環境や自然まで、全部つながった中で生まれるものだと思うんです」
ゆえに課題も多い。たとえば登り窯を造れる職人が減っていることや、唐臼を造る唯一の職人が高齢であること。
「唐臼でゆっくり砕く“均一すぎない土”や、薪の炎で長時間かけて焚く登り窯がなければ、小鹿田の器にはなりません。薪にする古材や廃材も近年は規制で手に入らない。小鹿田焼は19
95年に国の重要無形文化財になって、陶工の技術は守られていますが、大工技術や農業といった日本の文化そのものも、国全体で守り育てていく必要があると思うんです。小鹿田焼は自然と切り離せない焼きものですから」
そんな〈小袋窯〉の次代を担うのが、長男の杏梓さん、22歳。佐賀県有田の窯業高校で学んだ後、岐阜県の多治見で修業し、昨年小鹿田に戻ってきた。
「一度、小鹿田の外へ出たのは、いろいろ見て知っておきたかったからです。仲良くしてもらっている(坂本)創さんも、鳥取の窯元で2年修業してから戻ってきた。地域によって土の特徴も釉薬の出方もろくろの方法も違うので、それを体に入れておくことで、表現の幅も広がるような気がしたんです」
まだ勉強中だと話す杏梓さんだが、グラフィカルな掛け分けや素朴な飛び鉋の皿がSNSで注目され始めている。
杏梓さんの器も、それから創さんの皿も、使っているのは地元の土に蹴ろくろに登り窯。つまり昔と同じやり方だ。でありながら、そのフレッシュな意匠や佇まいは、新たな小鹿田焼ファンの心をギュッと掴んでいる。
のどかな里山の変わらない風景と、変わらない手仕事に息づく新しい感性と。小鹿田焼300年の伝統は、これからもそうやって受け継がれていく。
小袋(こぶくろ)窯
黒木家から分家した窯元。意匠は端正で柔らかな印象。先代(道明さんの父)も現役で、併設の販売所には3世代の器が並ぶ。8年前に登り窯を造り直した際、伝承者が減っていく窯造りの技術を少しでも学ぶべく、父子で築窯に参加した。
●大分県日田市源栄町170
小鹿田焼陶芸館
江戸末期~現代の作品を展示しながら小鹿田焼の歴史や技法、特徴を紹介。あまり目にすることのない大正以前の庶民の雑器など、貴重な古陶も見ることができる。
●大分県日田市源栄町138-1 TEL:0973-29-2020 9時~17時 水曜休(祝日の場合は翌日休)
『クロワッサン』1150号より
広告