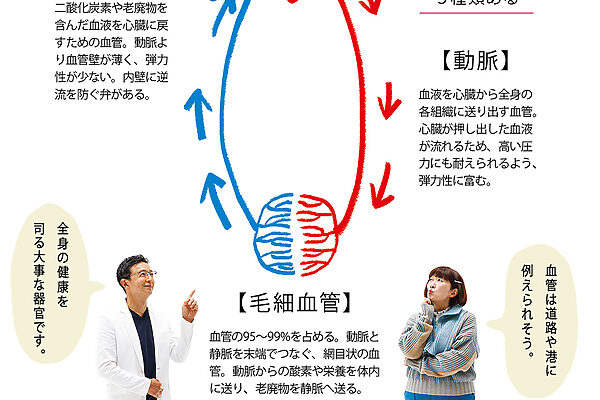「犬と暮らすこと」作家・辻 仁成──「犬と猫のいる暮らし」より
文・辻 仁成

息子が大学生になって巣立ち、ついにぼくは一人になった。そんな日がいつか来ることはわかっていたから、ぼくは先手を打って、息子が高校生の頃に、「未来の愛犬」探しを始めた。そして、3年前、ぼくはミニチュアダックスフンドの三四郎と出会った。神経質なぼくが、果たして犬を育てることができるのかわからなかった。しかし、子供の頃からの夢だった「犬との暮らし」で癒され、自分の日常に意味と生き甲斐を持ちこみたい、と思うようになっていた。
同時に、不安もあった。ぼくはものすごく神経質なうえに、表現者なので創作に没頭すると周囲が見えなくなってしまう。ぼくのような風変わりな人間が、生き物を育てることができるのか、という不安は大きかった。「犬臭あるよ」「うんちもさせないとならないよ」「散歩も必要だよ」「病気になることもあるし、人間よりうんと寿命は短いよ」などなど、犬を飼った経験者から、たくさんの忠告を受け、正直、悩んだ。犬を飼い続ける責任と自信が自分にあるのだろうか。
しかし、三度のロックダウンに見舞われたコロナ禍の終盤、ぼくは、人生の伴侶となる犬を探し始める。フランスでは、専門のブリーダーから犬を譲り受けないとならない。犬を飼う資格があるのか、審査を受けた。ぼくは健康状態が良好なことを説明し、ブリーダーさんに強い決意を語り、何度か通って、最終的に三四郎を委ねて頂けることになった。「犬を飼う」という感じではなく「天から授かった」という意識に近い。
我が家にやって来た最初の日、三四郎はキャンキャン鳴き続けた。だから眠れなかった。こりゃあ、思った以上に大変だぞ、と途方に暮れた。そこら中で、おしっこもうんちもするし、かなりの破壊魔で、ソファとか家具が次々壊れていった。しつけないとならない、でも、どうやって?
ドッグトレーナー協会に入会した。最初の一年は毎週、バンセンヌの森の犬の訓練に参加した。その甲斐あって、三四郎は少しずつ、成長した。外でおしっこもうんちもできるようになり、ものを壊さなくなった。ぼくの傍に寄り添い、気が付くと、ぼくは彼の存在に癒されていた。
ここ数年、「小さく丁寧に生きる」人生へとぼくは舵を切った。その柱の一つに愛犬との暮らしがある。おかげで、規則正しい生活をおくることができるようになったし、寂しくなくなった。
息子も三四郎に会いに頻繁に戻って来るようになったし、三四郎はみんなに好かれるので、彼が人をどんどん繋いでいくことになった。犬を通した友人や知り合いが一気に増えた。
ミニチュアダックスフンドの寿命は15年ほどなのだそうで、ぼくは今、65歳だから、77歳くらいまでは一緒にいられるのかなぁ。
先のことを考えると、実は、寂しい。でも、愛をたくさん注げば、もしかするともう少し長く一緒にいられるかもしれない。長生きをしてもらいたいので、チキンと白菜を煮て、毎日、ドッグフードに混ぜて食べさせている。夕食後は、寄り添って、静かな時間を過ごす。ぼくの歌を三四郎はじっと聞いている。
きっと、これを「幸せ」と呼ぶのかもしれない。
息子が帰って来ると、三四郎は尻尾を振りながら、息子に飛びついている。そこに、人生の第三楽章へと向かうぼくの穏やかな「家族の姿」があった。

『クロワッサン』1140号より
広告